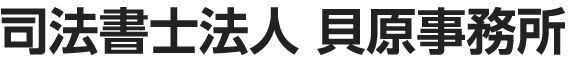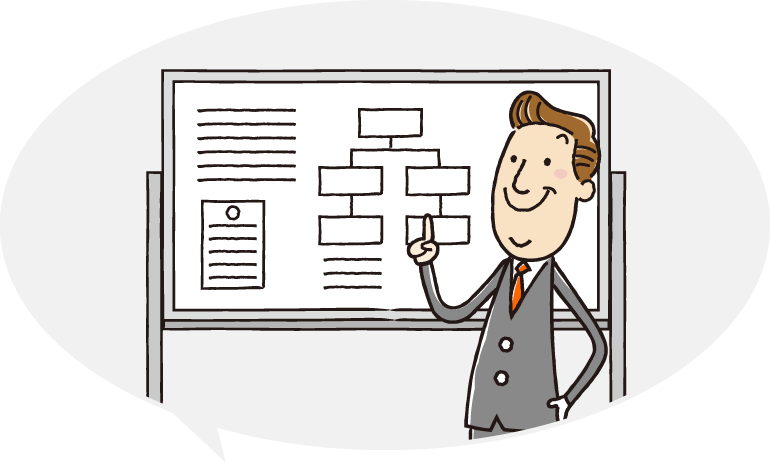相続・不動産登記・会社設立・成年後見など
沼津市の司法書士法人 貝原事務所がお応えします。
私ども司法書士法人 貝原事務所は、沼津・三島などの静岡県東部地域において司法書士サービスを提供する、開業25年目の司法書士事務所です。
- 相続登記・抵当権抹消登記・会社設立登記などの各種登記
- 遺言作成、預貯金・不動産等の遺産承継など各種相続手続きのサポート
- 成年後見制度の利用支援(開始申立て、親族後見事務、任意後見契約の締結など)
- その他司法書士業務
皆様からのご依頼に一つ一つ丁寧に対応してまいります。
ご相談の流れ
ご相談=ご依頼ではありません。
貝原事務所でのご相談からご依頼までの流れをご案内いたします。


よくある質問
司法書士の業務内容で、貝原事務所に寄せられるご質問をまとめました。
新着記事
- 株式会社の吸収合併の手続きについて
 「吸収合併」とは、消滅する会社の権利義務の全部を存続する会社に承継させる手続きのことをいいます。この記事では「おおまかな吸収合併手続きの流れを確認する」ことを目的として、ポイントを絞って手続きの内容をチェックしていきます。
「吸収合併」とは、消滅する会社の権利義務の全部を存続する会社に承継させる手続きのことをいいます。この記事では「おおまかな吸収合併手続きの流れを確認する」ことを目的として、ポイントを絞って手続きの内容をチェックしていきます。 - 合同会社について(株式会社との比較、設立手続き)
 会社を設立する際に「合同会社」を検討する方が増えています。合同会社の特徴、株式会社との比較、設立手続きのポイントについて確認をしてみましょう。
会社を設立する際に「合同会社」を検討する方が増えています。合同会社の特徴、株式会社との比較、設立手続きのポイントについて確認をしてみましょう。 - 沼津市で「預金・貯金」の相続手続きにお困りの方へ
 預金・貯金の相続手続きって、どう進めればよいのでしょうか?意外と手間・ヒマのかかる預金・貯金の相続手続きについて、沼津の司法書士が解説します。まずは、預金・貯金の相続手続きの流れを確認したうえで、気を付けるべきポイントをチェックしていきましょう。
預金・貯金の相続手続きって、どう進めればよいのでしょうか?意外と手間・ヒマのかかる預金・貯金の相続手続きについて、沼津の司法書士が解説します。まずは、預金・貯金の相続手続きの流れを確認したうえで、気を付けるべきポイントをチェックしていきましょう。
- 株式会社の吸収合併の手続きについて
- 合同会社について(株式会社との比較、設立手続き)
- 沼津市で「預金・貯金」の相続手続きにお困りの方へ
- 医師・歯科医師の診療所の相続
- 株式会社の解散・清算結了の手続きについて
司法書士への相談事例
貝原事務所にて取扱った事例をご紹介します。
「こんなキッカケで司法書士を利用するんだね。」とか、「実は、こんな課題や解決方法があったのね。」とか感じていただければ嬉しいです
報酬額一覧
標準的な司法書士費用の目安をご案内いたします。
司法書士法人 貝原事務所
宮町事務所
〒410-0851 静岡県沼津市宮町85番地
(旧住所表記: 静岡県沼津市宮町441-22)
TEL 055-963-3537
若葉町事務所
〒410-0851 静岡県沼津市若葉町17-28
TEL 055-921-5000
| 代表番号 | 055-963-3537 |
宮町事務所
若葉町事務所