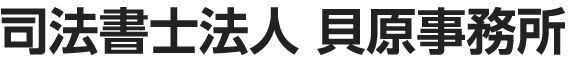目次を表示
1.遺言って堅苦しいもの?
(1)遺言のイメージは
遺言というと、非常に堅苦しいイメージがあるかと思います。
また、「遺言≒相続争い」というイメージもあるかもしれません。
さらには、「お金持ち=遺産がたくさんある人が作成するもの」というイメージもあるかもしれません。
極端な例をあげれば、つぎのような横溝正史映画にあるような、一場面でしょうか。
地元の名士である大資産家・沼津太郎が死去した。
相続人は仲が悪く、葬儀の場でも、既に言い争いが起きているような状況である。
そこに突然、被相続人の顧問弁護士・三島一郎氏が登場し『沼津太郎氏から遺言を預かっています』との発言。
色めき立つ相続人たち。親族が静まりかえる中、三島一郎氏は淡々と、沼津太郎の遺言を読み上げる。
遺言の内容は、なんと富士一太郎という、誰も知らない青年が遺産のすべてを承継するというもの。同席した相続人らは、三島一郎氏に詰め寄る。
三島氏によると、富士一太郎は沼津太郎の子だというが・・・。
(2)どうしても遺言は堅苦しくなる
どうでしょうか。ここまで極端ではなくとも、上記のような場面は、皆様の遺言に対するイメージに重なるところがあるのではないでしょうか。
遺言の堅苦しさは、こうして作り上げられたイメージによる部分もあるかもしれないのですが、遺言の特性から考えても仕方がないところがあるのです。
2.遺言の特性
(1)遺言者の死亡後に効力が発生する
遺言は、遺言を作成した人が亡くなった後に効力が発生するものです。効力が発生するときに、遺言者はいませんので、遺言書の意味が分からないときに「これは○○という意味なのだ。」とか「ちょっと言葉が足りないので補足すると・・・。」ということはできません。
これが、契約書であれば、もちろん紛争になってしまっては話し合いの余地はないでしょうが、まずは当事者で話合いをし、意味を特定したり、補足を行ったりすることができるでしょう。
(2)曖昧さを避ける、解釈の余地をなくす
したがって、遺言作成に際しては、曖昧な言葉を避け、解釈の余地を極力少なくすべきということになります。
そうした方針で作成していくと、結局のところガチガチの法律文書が出来上がってくるのです。
こうして作成された遺言に対して、多くの人は「堅苦しい」というイメージをもつことになるでしょう。
3.遺言の堅苦しさを緩和する方法?!
(1)どうしても堅苦しくなります
「堅苦しくない遺言を書きたい」というご要望に対しては、「残念ながら、どうしても堅苦しくなります。」とお答えしています。
それは、遺言の主たる役割を果たすためには、どうしても「曖昧さを避ける、解釈の余地をなくす」ことが求められるからです。
そこで、「堅苦しい部分」と「やわらかい部分」を共存させる方法があります。それが付言事項の活用です。
(2)付言事項の活用
付言事項とは、遺言者の気持ち・想い」「遺言の記載理由」を相続人等に伝えるものです。付言事項に関する詳細は、下記の参考記事をご覧いただきたいのですが、こうした「気持ちを伝える部分」を添えることで、遺言全体のイメージはグッとかわります。
(3)シンプルな遺言
また、少し考え方はかわりますが、細かく緻密にガチガチに遺産分割方法について記載していなくても遺言は作成することができます。
その一例が、「私の相続財産の一切を、配偶者○○に相続させる」というような一文から構成されるシンプルな遺言です。詳しくは、下記の参考記事に記載していますので、興味のある方はご覧ください。