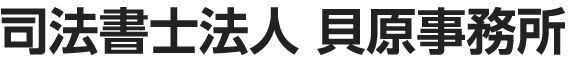目次を表示
1.相続は死亡によって開始する
そもそも相続は、ある方の死亡によって自動的に発生します。
相続人は、自動的に、亡くなられた方の権利義務を承継するのです。
そのうえで、相続人が相続の効力を拒否したい場合には、特定の手続きをとる必要があるのです。
相続の効力を拒否したい理由は相続人によって様々です。
あくまで一例ですが、つぎのような理由を良く耳にします。
- 財産よりも借金のほうが多いから。
- 疎遠であったため、債務があるか不安。
- 疎遠であったため心情的に相続を遠慮したい。
- 幼少期より別に暮らしており、相続に関与したくない。
司法書士の業務として、相続放棄に関わっていると、意外と心情的な理由で相続放棄をする方が多いことに驚きます。
2.相続の効力を否定する場合
(1)相続放棄
相続の効果全部を拒否したい場合には、「相続放棄」の申述を家庭裁判所に対して行います。
相続放棄の手続きは、ご自身に相続があったことを知ってから3カ月以内に行われなければならないので注意が必要です。
また、のちほど説明しますが、相続財産を処分すると「相続を単純承認した」として、3カ月前であっても相続放棄ができなくなります。この点も注意が必要です。
(2)限定承認
相続放棄は相続の効力全部を否定するものでした。
限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産を清算し、プラスの財産が多かった場合には、その剰余の部分を相続するというものです。
非常に良い方法と思われますが、相続人全員が共同して行う必要があったり、限定承認の手続きや税制が複雑で費用も掛かるなどの理由で、あまり活用されていないのが実態です。
3.法定単純承認
単純承認とは、確定的に相続の効力を承認することです。単純承認する場合には、とくに「単純承認します」と宣言する必要はありません。
つぎのような法定単純承認事項が定められており、これに該当すると単純承認したものとみなされます。
(1)相続財産の処分等
相続財産の処分等をおこなうと、相続を承認したものとみなされます。相続財産の処分は、自らを相続人と自認したものと考えられるからです。
なお「処分」とは、遺産を破棄するという意味だけではなく、売却したり、遺産物協議を行ったりということを含みます。
一般的な言葉の意味よりも範囲が広いので、相続放棄を検討している場合には注意が必要です。
(2)相続を知ってから3カ月が経過
自らが相続人となったことを知ってから3カ月経過した場合にも、単純承認をしたものとみなされます。
したがって、相続放棄や限定承認をしたい場合には、相続開始を知ってから3カ月以内に対応しなければなりません。
ある程度、相続財産の内容を相続人が把握しているケースであれば問題はないのですが、疎遠の相続人の場合には、すみやかに相続財産の調査に着手する必要があります。
なお、3カ月の単純承認期間を延長することを家庭裁判所に求めることもできるので、必要な場合には延長手続きを行うこともできます。
4.3カ月経過後の相続放棄について
相続開始から3カ月経過後あるいは法定単純承認事由が生じた後の相続放棄については、いくつか例外的な事由が裁判例によって認められています。
具体的な事案における相続放棄の可否は、法律専門職に相談しながら手続きを進めるべきでしょう(最近は「相続放棄無効の裁判」をおこす債権者も増えているので、ケースによっては最初から弁護士に相談すべきです。)。