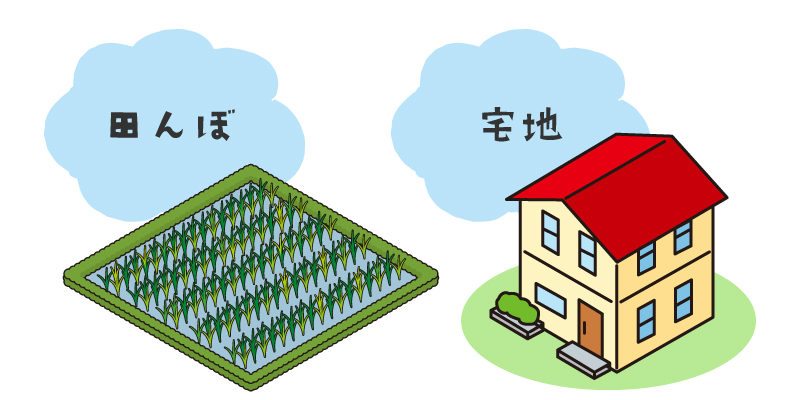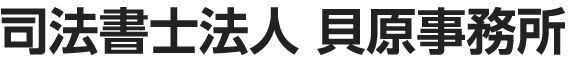目次を表示
1.相続登記って?
(1)相続登記とは
相続登記とは、亡くなられた方(被相続人といいます。)が所有していた不動産について、その不動産を引き継ぐ相続人の名義に変更する手続きのことをいいます。
相続登記といっても、実は、さまざまなパターンがあります。
この記事では「亡くなった方の不動産について、複数の相続人のうちの1名が、話し合いにより承継していく。」というシンプルなパターンを前提に、相続登記の進め方を確認していきます。
(2)相続登記の流れ
相続登記の、4つの大きなステップは、つぎのとおりです。
- 戸籍集めによる相続人の確定
- 相続登記をすべき不動産の調査
- 相続人同士で不動産を取得する人を決定(遺産分割協議)
- 相続登記を法務局に申請(必要書類とともに)
(3)相続登記についての関連記事
この記事では、いよいよ「相続登記の法務局への申請」と題して、申請手続きの基本的なところを確認していきます。
その他のステップについて確認したいという方は、つぎのリンクから各手続きの詳細をご覧ください。
2.相続登記の申請前の準備
(1)申請すべき法務局を確認する(相続登記の管轄法務局)
相続登記の申請は、各地域の法務局でおこないます。
法務局には「管轄」があり、土地・建物の所在地ごとに、相続登記の申請をおこなう法務局は異なります。
当事務所のある沼津市周辺だと、つぎのような管轄になっています。
| 管轄する市町 | |
| 沼津支局 | 沼津市 裾野市 御殿場市 三島市 伊豆市 伊豆の国市 駿東郡小山町,清水町,長泉町 田方郡函南町 |
| 富士支局 | 富士市 富士宮市 |
| 熱海出張所 | 熱海市 伊東市 |
| 下田支局 | 下田市 賀茂郡南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町 |
ちなみに、法務局に対する登記の申請は、郵送やオンライン(事前準備が必要)でも可能です。
管轄を調べるときには、「(物件の所在市町)+登記申請+管轄」でネット検索すると、確認しやすいかもしれません。
例:「三島市 登記申請 管轄」
(2)相続登記の申請書と必要書類を確認する
相続登記を申請する法務局が確認できたのであれば、つぎは申請書と必要書類を確認してみましょう。
パターンごとに、いろいろな書類が必要となりますが、オーソドックスな書類としては、つぎのとおりです。
- 登記申請書
- 被相続人と住民票除票(本籍付き)
- 被相続人の相続関係を確認できる戸籍一式
- 相続人全員の現在の戸籍
- 相続人全員の住民票(本籍付き)
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産税納税通知書または名寄帳
以上の書類は、別の書類で代替ができたりすることもあれば、逆に追加で別の書類が必要となることもあります。
ここから先は、ほんとうにケースバイケースなので、ご自身で相続登記を進めたい方は法務局に確認してみるのが良いでしょう。
(3)相続登記の申請者は「不動産を取得する人」!
なお、相続登記の「申請人」となるのは、相続した不動産を取得する人となります。
たとえば、お父さんが亡くなり「母と子」が相続人となったケースにおいて、母が不動産を単独で相続することになったのならば、相続登記の申請人は「母」となります。
ある不動産を母、別の不動産を子が、それぞれ単独で相続する場合には、母と子がそれぞれ別々に申請をする必要があります。
このあたりから、「相続登記」に独特なルールが登場し、ご自身で相続登記を進めようと思ってらっしゃる方を悩ませてしまうかもしれません。
(4)相続登記の申請には「登録免許税」が必要!
さらに、相続登記の申請には、法務局の納める手数料が必要となります。
取得する不動産の固定資産税評価額に0.4%を乗じた金額が、原則的な計算方法となります。
固定資産税評価1000万円の土地であれば、4万円を登録免許税として法務局の納めることになります。
お金を払うのではなく、収入印紙を購入し申請書に貼って提出するのが一般的です。
(オンライン申請であれば、ネットバンキングも利用可能です。)
ただし、現在、相続登記を促進する観点から「免税措置」が定められており、これらに該当すれば登録免許税はゼロ円になります。
詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
3.相続登記申請書を法務局に提出してから完了まで
(1)相続登記の申請書の記載方法は難しい!
相続登記の申請書の記載の仕方については、ケースバイケースになるため、詳細を知りたい方は、法務局のホームページや、一般の方向けに記載された書籍を参考にされることをお勧めいたします。
とくに勘違いされる方が多い箇所は、つぎの2つです。
- 不動産を承継した人が、相続登記の申請人となる。
(相続人A・B・Cのうち、不動産を承継したのがBならば、Bが申請人となる。) - 承継した人が異なる場合、相続登記の申請をわける必要がある。
(土地を相続人A、建物を相続人Bが取得したなら、相続登記の申請は2つになる。
Aが申請人になるものと、Bが申請人になるもの。)
ご自身で相続登記の申請をされる方で、申請書の記載方法に悩む方は、法務局で申請書の記載について相談をされるのが早いかもしれません。
(2)相続登記の添付書類
相続登記の添付書類は、さきほど簡単にご説明しました。
添付する書類を、おおまかに分類すると、つぎのようになります。
- 被相続人(亡くなられた方)の相続人を確認するための書類
- 被相続人と現在所有者として登記されている方が同一人物であることを確認する書類
- 相続人の本籍と住所を確認するための書類
- 相続人全員で話合いが行われたことが確認できる書類。
(同時に、誰が不動産を取得したが確認できる書類。 - 登録免許税を算定するために必要な書類
(3)添付書類の原本還付を忘れずに
相続登記の際に、法務局に提出する添付書類については、いちど原本を法務局に提出する必要があります。
ただし、相続人全員に押印をもらった遺産分割協議書や印鑑証明書など、不動産以外の相続手続き(たとえば預貯金)でも利用可能なものがあります。
そうした書類については、原本還付と言う手続きを取ることによって、原本を法務局から返してもらうことができます。
原本還付の手続きは、簡単に説明すると次の通りです。
- 原本のコピーを用意する。
- コピーの余白に「上記は原本に相違ない。」と記載し、申請人が記名押印をする。
- 原本と一緒に法務局に提出する。
このほかにも、戸籍関係については「相続関係説明図」を作成することで、より簡単に原本還付を受けることができます。
(4)相続登記の受付から完了まで
相続登記の申請書を法務局に提出してから、法務局での登記処理が完了するまでに、おおむね1週間から2週間程度かかるのが通常です。
また、申請書や添付書類に不備がある場合には、法務局から補正の通知がなされます。
この補正通知に対応しないあいだは、登記処理は進まないため、それだけ完了までの期間が長くなることになります。
完了までにかかる時間は、管轄、法務局ごとの処理期間にもよりますし、補正通知にスピーディーに対応するかどうかによっても大きく変わってきます。
(5)相続登記の完了書類も大切に!
相続登記が完了すると、法務局から「登記識別情報通知」という書類を受け取ることになります。
この登記識別情報というのは、昔でいうところの土地・建物の「権利証」です。
たとえば、相続登記が完了した後に、その土地・建物を売却するという方もいらっしゃると思います。
不動産を売却したときにも登記(所有権者の名義変更)が必要となるのですが、その登記手続きにおいて「相続登記をした際の登記識別情報」を利用します。
この「登記識別情報」は紛失しても、再発行されません。
登記識別情報が必要な手続きで提出できないと、余計な手間や費用がかかる可能性が大きいです。
登記識別情報通知も含め、完了後の書類の管理には注意してください。
4.相続登記の申請は自分でできる?専門家は?
(1)相続登記の申請は自分でできる
相続登記の申請は、必ず専門家(司法書士)に依頼しなければならない、と言うことではありません。
むしろ、法律上の原則は、申請される方、ご本人が申請することを前提としています。
一方で、ここまで記事を読んでいただくと、相続登記には、一般の方には把握しづらい細かなルールが定められていることがわかるかと思います。
(2)最後の申請段階で困ってしまう方も・・
インターネット上で、相続登記について検索をすると、相続登記の申請の仕方について解説したページをたくさん確認することができます。
相続登記の申請書についての記載方法や、添付する遺産分割協議書の書き方、戸籍等の添付書類の集め方が丁寧に解説されています。
一般の方が、登記制度に関係する場面は少ないと思いますので、相続登記によって登記制度に関わりをもっていただくことは、登記制度を支える司法書士としては、とても嬉しいことです。
一方で、当事務所には「相続登記を自分でやってみようと挑戦したけれど、やはり難しくて専門家に依頼することにした。」ということで、ご依頼をいただくケースが少なくありません。
専門家への依頼に切り替えた理由としては、つぎの2つの理由をあげられる方が多いです。
- 相続登記の申請書の書き方がわからない。
書籍を見ても、いろいろなパターンがあって、自分のケースに該当するパターンが特定できない。 - 相続登記の申請は法務局に出す必要があるが、法務局の開庁時間は平日日中に限られている。
くわえて、申請書や添付書類の補正があると、たびたび法務局に足を運ばなければいけない。
(3)相続登記の専門家は司法書士
私たち司法書士は、登記を専門に取り扱う職業です。
相続登記についても日常的に取り扱いをしております。
相続登記の申請について、専門家に依頼をしたいと言うことであれば、ぜひ身近な司法書士にお声掛けをください。
5.相続登記を任せるなら司法書士に!
(1)沼津や三島などの沼津近隣の方なら
身近な司法書士となると「名前を知っている司法書士」や「依頼したことのある司法書士」ということになるかと思います。
沼津や、三島市などの沼津近隣にお住まいの方で、そうした司法書士がいないということであれば、ぜひもと当事務所(沼津の司法書士貝原事務所)にお声がけください。
(2)身近な司法書士の探し方
申請人(相続人)は沼津市や三島市にお住まいだけれど、相続登記をすべき土地や建物が遠方にあるというケースもあります。
その場合でも、司法書士であればオンラインで遠方の法務局にも申請をだすことができます。
ですから、わざわざ不動産の所在地の司法書士に依頼する必要はなく、相談者さんの身近なところにいる司法書士に声をかけてください。
各都府県ごとに司法書士会が設置されており、また各司法書士会のHPにおいて司法書士会員を検索することができます(北海道だけは道のなかに4つ)。
6.沼津の司法書士貝原事務所が紹介する「相続登記の進め方」
(1)「相続登記の進め方」に関連する記事
この記事(「相続登記の進め方」)は、正しく相続手続きが進められるように、また専門家に相続手続きを依頼したいと思ったときの相談先(司法書士)があることを知っていただきたいという思いで制作しました。
この記事のほかにも、シリーズになっていますので、興味があれば、ぜひご覧ください。
(2)相続登記の進め方(沼津の司法書士が解説!)
つぎの記事⇒〇相続登記の進め方【6:不動産以外の相続手続き】
この記事⇒〇相続登記の進め方【5:法務局への申請】