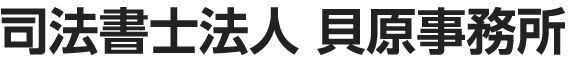守秘義務および個人情報保護の観点から、実際の事案を変更・編集して記載しています。
土地・建物・預貯金の相続手続き
依頼者はAさん。(静岡市在住)
お父様が亡くなり、相続人はお母様B(沼津市在住)さんと妹Cさん(関西圏在住)の3名でした。
土地・建物の相続と、預貯金の相続があり、どのように手続きを進めていけばよいかとのご相談からスタートしました。
遺産分割協議書の作成、相続税の申告手続き
相続人が複数いる場合に、不動産名義を変更したり、預貯金を承継したりするためには、相続人間での遺産分割協議が必要となります。
協議を行い、遺産の分け方を決定したうえで、それらを遺産分割協議書にまとめたり、金融機関への届け出書類に実印にて押印を行います。
分割の仕方はだいたい決まっているけれど、果たしてどのように手続きを進めればよいのかは、はじめて相続手続きを進める方にとっては、疑問が多いところでしょう。
くわえて、今回のケースでは、初回相談の際に、相続税申告が必要と思われる案件でした。
以前は、相続関係の業務をしていても、さほど相続税が関係することは少なかったのですが、平成27年に相続税法の改正以降は、実際に課税されるケースは少ないのですが、検討が必要となったり、申告が必要となるケースが非常に増えている印象です。
そこで、今回のケースでは、税理士さんへ相談することをお勧めしました。
結果として、承継方法を若干変更して、各種相続税制の利用により、相続税申告は行ったものの、課税自体はゼロとなりました。
具体的な相続登記の進め方としては、以下のとおりです。
- AさんとBさんに来所していただき、初回相談。見積提示の上、後日、正式に業務依頼をいただく。
- 相続税申告の必要性が疑われたため、税理士さんをご紹介。
- 結果、分割方法の検討が必要とのことで、税務申告につき依頼。
- 税務申告を踏まえたうえでの分割方法をAさん、Bさん、Cさんの3名で決定していただく。
- 決定内容をもとに、弊所にて遺産分割協議書を作成。
- 3名のご了解をいただいたうえで、弊所をハブにして、郵送にて遺産分割協議への捺印を行う。
- 不動産取得者のBさんから、あらためての相続税に関する検討を加味して、分割方法を相続人3名の方に決めていただきました。
- その後、各相続人に連絡の上で、弊所をハブにして、遺産分割協議書への捺印を実施。
- Bさん宅に伺い、不動産登記の委任状に捺印をいただく。弊所にて、登記手続きをすませ、完了書類をBさん宅に持参。
- 預貯金については、Cさんが対応。
- 税理士さんから相続税申告を行い、一連の手続きが完了。
PICK UP

相続登記が必要なケース、相続登記をしないとどのようなトラブルが起こりやすいか?自分でも登記は可能なのかについて詳しく解説します。