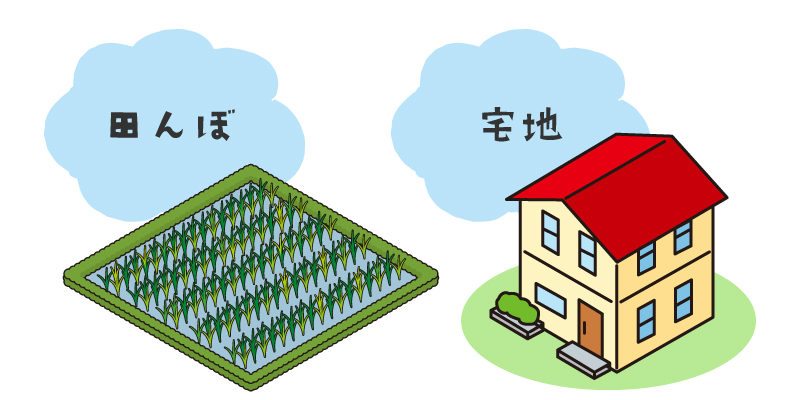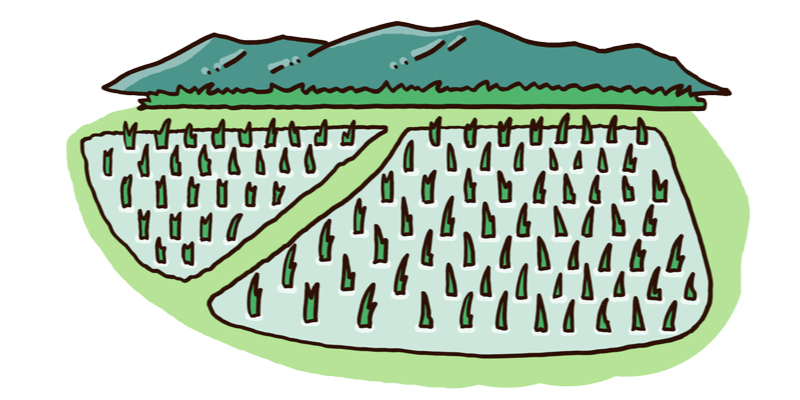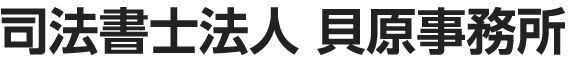目次を表示
1.農地法との関係
(1)農地の売買と農地法
農地を売買する場合、「農地法」という法律による許可が必要となります。
この許可の手続きは、基本的には各市町の農業委員会が窓口となっており、農業委員会に所定の申請をして進めていくことになります。
許可の要件は厳密に定められており、対象となる農地が特定の区域にあると、それだけで「不許可」となることもあります。
農地は、それだけ厳重に保護されているのです。
(2)農地の売買による名義変更(所有権移転登記申請)について
許可がなくとも個人間で売買契約を締結することはできますが、農地の所有権移転の効力は発生しません。
そのため、許可なしに所有権移転登記(売買による名義変更)をすることはできません。
法務局では、登記された地目が「農地」である場合には、農地法所定の手続きが済まされているかを確認します。
確認の結果、「農地法の手続きに不備」ということが判明すれば、所有権移転登記申請は却下されることになります。
2.農地のまま売買(農地として利用)
農地を、農地として利用する目的で売買する場合、農地法3条の許可が必要となります。
許可の条件としては、主につぎのようなものがあります。
- 耕作する農地の全部を効率的に利用すること
- 権利を取得する者またはその世帯員等が、農作業に常時(原則、年間150日以上。)従事すること。
- 下限面積以上の農地を経営すること
- 周辺農地の利用と調和すること
とくに2点目に注目してほしいのですが、農地の売買の場合には、買い手の耕作能力も必要となってくるのです。
3.転用して売買(農地以外の目的で利用)
農地を、農地以外の方法で利用することを目的として売買する場合、農地法5条の許可が必要となります。
許可の条件としては、「立地基準」「一般基準」という2つの基準があります。このうち「立地基準」については、農地の種類によって定められているものです。
農地の種類については、別記事にまとめていますのでご参照ください。
【参照記事:農地法の種類と許可の方針について】
「一般基準」のうち代表的なものは以下のとおりです。
- 転用目的どおりに確実に土地が使用されると認められること。
- 周辺農地の農地経営に影響(土砂の流出や排水など)を与えるおそれがないこと。
- 一時的に農地を農地以外に利用する場合には、利用後に確実に農地に復元すること。
従って、そもそも「立地基準」で門前払いされるケースもありますし、立地基準を満たすとしても、上記の一般基準を満たすような申請でなければ「不許可」ということになります。
4.許可ではなく届出で良いケース
これまでの説明では「許可」を取得しなければならないと説明してきましたが、許可ではなく「届出」で足りる場合があります。
その代表例が、「市街化区域内の農地」である場合です。
市街化区域内の農地の場合には、転用や転用を伴う権利移転の場合においても、許可ではなく届出で足りることとなっています。
なお、届出といっても紙切れ一枚を提出すればOKというようなものではなく、各市町で定められている「届出書+添付書類」が必要となりますので、ご注意ください。