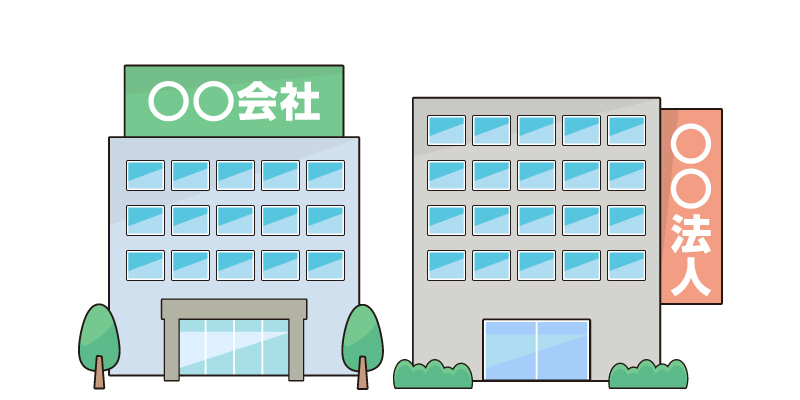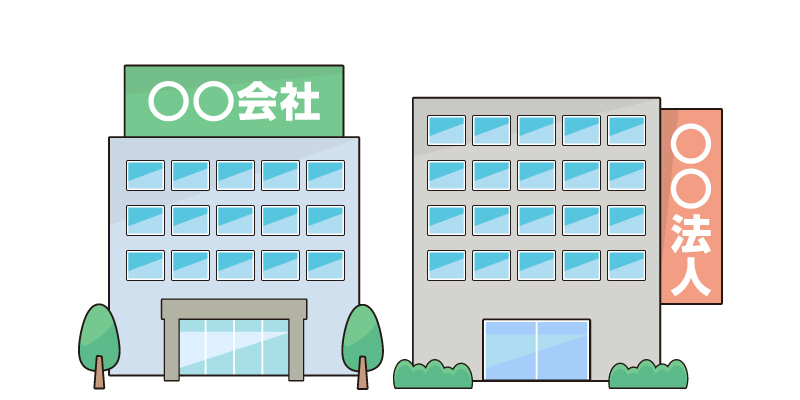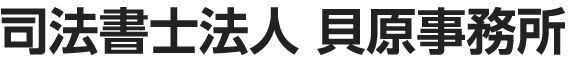目次を表示
1.「株式」も相続の対象
発起人として会社を設立すると、当然ながら設立後の会社の株式を取得します。
この株式は、株式市場によって売買されている「上場株式」と同様に、財産的価値を持つものなので相続の対象となります。
ただし、会社を設立し取得した株式については、財産的価値だけでなく、議決権(経営権)を考慮して相続に対応する必要があります。
議決権が重視される株式を、本記事では「自社株式」と呼ぶこととします。
2.自社株式を複数の相続人が相続した場合
(1)自社株式は共有される
自社株式は相続の対象となります。
そして複数の相続人がいる場合には、その相続人間で「共有」されます。
この共有状態は一時的なものであり、誰が株式を相続するか確定させるためには遺産分割協議が必要となります。
なお、仮に100株の株式が相続されたとして、相続人が子2名であった場合、100株を2名で共有することになります。
子それぞれが50株ずつ取得するわけではないので注意してください。
(2)株式の共有状態で開催する株主総会
自社株式が相続によって共有されている状態のまま株主総会が開催される場合には、議決権行使のために「権利行使者」を1名定める必要があります。
この権利行使者の指定は、共有持分の過半数で決定します。
さきほどの例でいえば、子2名の持分は等しいため、2名が合意しなければ権利行使者を指定することはできません。
権利行使者を指定できない場合には、議決権を行使することもできません。
(3)共有解消のための遺産分割協議
共有状態を解消するためには、相続人間で遺産分割協議をする必要があります。
相続人間での協議が難しい場合には、遺産分割調停や遺産分割審判などの裁判手続きを利用していくことになります。
(4)自社株式の相続対策は必要不可欠
以上のとおり、相続人間での話合いが円滑に進まない場合には、株主総会における意思決定すらできず経営がストップしてしまうことも想定されます。
加えて、相続によって株式を取得した相続人が、従来の株主同様の経営知識・経営能力を有しているかは不確かです。
経営に無関心ならまだしも、中途半端に関心を持つケースでは、経営陣がそれに振り回される恐れもでてくるのです。
こうした場合に備えるため、後述するような「相続人等株式売渡請求」や「遺言」などの対策をとる必要があります。
3.【対策例1】相続人等株式売渡請求
(1)相続人等株式売渡請求の概要
株式会社は、定款において「相続等により株式を取得したものに対し、当該株式を会社に売り渡すことを請求することができる」旨を定めることができます。
「売り渡す」なので、株式評価に応じた金銭を相続人に対して会社が支払う必要があります。
また、会社側には財源規制が課せられるため、無制限に買取ができるわけでもありません。
しかしながら、条件がそろえば「株式を売り渡す」ことを相続人に強制できるため、非常に強力な規定といえます。
(2)相続人等株式売渡請求の効果の見極めを
詳細は省略しますが、この売渡請求に関する規定は、状況や立場によって有利にも不利にもなる規定です。
意識することなく定款上に定めを置いている会社が少なくないので、設立時はもちろんのこと、設立後においても、定期的に売渡規定がどのように使用されうるのか確認する必要があるでしょう。
4.【対策例2】遺言
(1)遺言の効用
上記2(2)で例示したように、相続人が複数いる場合には、自社株式が遺産分割の対象となります。
自社株式そのものの奪い合いになることもありますし、自社株式を特定の相続人に集中させるために分割割合が不平等となるために揉めるということもあります。
遺産分割を回避するためには、遺言を作成し、株式を含めた遺産の承継先を決めてしまうことが非常に効果的です。
正しく遺言を作成すれば、遺産分割は省略されるのです。
(2)相続税や遺留分への対応
遺言によって、自社株式を含めた遺産の分割方法を指定する場合には、自社株式の評価が必要となります。
自社株式の評価は、遺産全体の金額(ひいては相続税)に関係してくるものであり、また遺留分を推計する場合にも必要となります。
自社株式の評価は、法人の税務申告を担当している税理士に確認するのが確実でしょう。
あわせて、相続税に関しても相談できるのであれば、なお良いでしょう。
5.株式会社設立に関する手続は当事務所にご相談ください
(1)株式会社・合同会社・一般社団法人等の設立手続き
当事務所では、会社・各種法人の設立手続きを、代行しています。
設立手続きにおいては、会社設立後の運営を見据えた、定款設計を心掛けています。
一部の営業許認可については、設立手続きと一緒に、当事務所司法書士(行政書士資格保有)にて対応することも可能です。お気軽にご連絡ください。
(2)ご依頼にあたっては原則面談を必要としています
ご依頼にあたっては、原則として、当事務所での面談が必要となります。
なお、沼津法務局管轄内の以下の市町については、事前にご相談いただければ出張も可能です。
沼津市・裾野市・御殿場市・三島市・伊豆市・伊豆の国市・富士市・富士宮市・熱海市
駿東郡小山町・清水町・長泉町
田方郡函南町