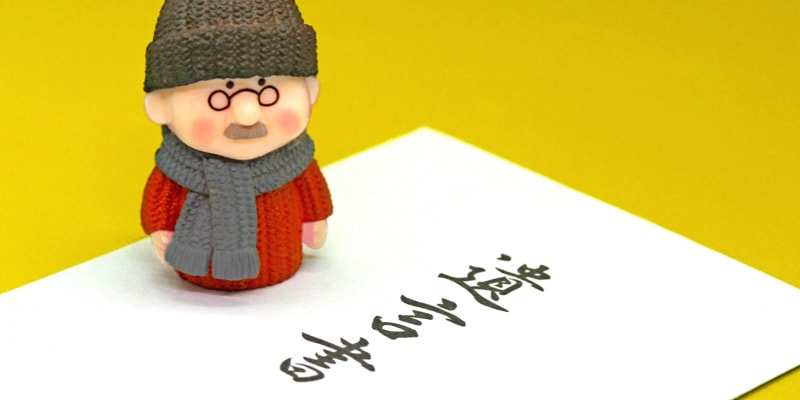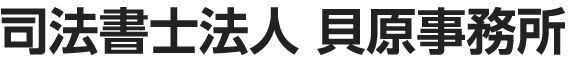目次を表示
遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所は、申立てにより、遺言執行者を選任することができます。
1.遺言執行者とは「遺言の内容を実現する者」
(1)遺言執行者がいない場合には・・
遺言の効力は、遺言者の死亡によって発生しますが、不動産の名義変更や預貯金の解約・承継など、遺言者の死亡後に各承継手続きが必要となります。
承継手続きに際しては、遺言の中で遺言執行者の選任がない場合には、遺言者の相続人全員が協力して手続きを進める必要があります。
(2)遺言執行者の選任によって「相続人全員の関与」を不要に
「相続人全員の協力が必要」とは、たとえば不動産の名義変更にあっては、遺言によって不動産を承継した人と遺言者の相続人全員が共同で登記の申請をする必要があるということです(たんに一緒に申請すればOKというわけではなく、実印の押印や印鑑証明書の添付が要求されます。)。
これらの手続きの手間を省くために、遺言執行者の選任は非常に効率の良い手段といえます。
2.誰が遺言執行者になれる?
法律上、いくつかの欠格事由(未成年者や破産者)が定められていますが、その他には資格の制限はありません。
そのため、遺言執行者は、受遺者自身や相続人の1人でもなることが可能です。
(当然ながら、家庭裁判所により選任される必要があり、選任については家庭裁判所に裁量があります。)
3.遺言執行者による遺産承継手続きの進め方
(1)遺言執行者からの復委任
遺言執行者に選任されたものは自ら執行行為を行わなければならないのが原則です。
しかしながら、遺言執行者は復任権をもちますので、遺言執行者が適宜復代理人を選任し執行行為をスムーズに進めることも可能です。
たとえば遺言執行者には親族を指定し、指定を受けた親族は復任権を利用し、具体的な執行を専門家に委任する方法を選択することができます。
(2)法律専門職に遺言執行者となってもらうことも可能
また、そもそも遺言執行者を選任する段階で、法律専門職に遺言執行者への選任を依頼することも可能です。
相続財産が多岐にわたるケースや、不動産の売却など専門的な知識を要する場合には、検討すべきでしょう。
なお、具体的な選任申立てについては、下記の記事をご参照ください。