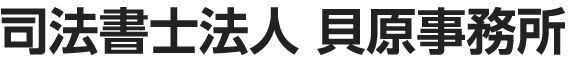目次を表示
未成年者が含まれる遺産分割においては、特別代理人の選任が必要となってきます。
特別代理人の選任申立てにおいて重要な点は、どのような遺産分割協議を予定しているかということです。
1.未成年者のために特別代理人を選任する必要性
(1)未成年者と親権者がともに相続人となる場合
遺産相続の手続きにおいては、亡くなられた方(被相続人)から引き継いだ遺産の分け方を相続人全員の話合いによって決めていく必要があります。
この話合いを「遺産分割協議」といいます。
相続人の中に、未成年者が含まれる場合には、未成年者本人に代わって、親権者が代理人として遺産分割協議に参加するのが原則です。
(未成年者が、単独ではスマートフォンなどを購入できないのと同じ理由です。)
しかしながら、遺産分割協議についても同じことが言えるのですが、相続の場面において注意すべきは、多くの場合、子だけでなく親権者自身も相続人となっているということです。
沼津市に在住のBさんからのご相談。
Bさんは、夫Aさんを亡くされました。
夫Aさんの相続人にあたるのは、配偶者BさんとCさんの2人です。
(Cさんは14歳。つまり未成年です。)
子Cさんの親権者は、当然ながら、母であるBさんとなっています。
(2)利益相反 → 親権者が未成年者を代理できない = 特別代理人
こうしたケースにおいては、BとCは「利益相反状態」にあるとされ、法律上、親権者が子を代理することができないことになっています。
したがって、このケースでは、親権者に代わって子を代理する「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。
こうした手続きを行わず、形式的に遺産分割協議書を整えてても、法務局や銀行等で手続きする際に、不備を指摘されることとなります。
2.誰が特別代理人となれるのか ~資格制限はない~
特別代理人の資格に制限はありません。
当事務所が関与した事例でよく見るのは、亡くなられた方の父母や兄弟姉妹(子にとっての叔父・叔母)です。
特別代理人の申立てにあたっては、誰がなるかよりも、後述するように、どのような遺産分割協議を予定しているかのほうが、重要となってきます。
3.家庭裁判所に対する特別代理人選任申立て
(1)未成年者が複数いる場合には、それぞれに対して選任
未成年の子が一人の場合には、未成年の子1名に対して、特別代理人の選任を申立てます。
未成年の子が複数いる場合には、それぞれに対して、特別代理人の選任を申立てます。
(2)【重要】申立てに際しては「遺産分割協議書案」の添付が必要
裁判所への申立てにあたっては、戸籍等の書類のほか「遺産分割協議書案」の添付を求められます。
この「遺産分割協議書案の添付」がポイントとなります。
裁判所では、協議書案のほか遺産目録等も要求し、子の法定相続分(次の項目で詳しく説明します。)が充足されているかをチェックします。
そのうえで、特別代理人の選任にあたっては、「別紙遺産分割協議書案のとおり分割するにつき、子Cの特別代理人としてXXを選任する。」というような形で提出された協議書案を援用して、裁判所が審判を行うのです。
4.未成年者の法定相続分への配慮について
(1) 未成年者の相続における最低限の利益の確保 = 法定相続分の重視
特別代理人は、 未成年者の利益を保護するために選任されるものです。
したがって、未成年者の利益(法定相続分相当の遺産)を確保することが原則となります。
「法定相続分」とは、法律上定められている各相続人の相続割合のことをいいます。
冒頭にあげた例では、相続人が配偶者Bと子Cの2人でした。
この場合、子の法定相続分は2分の1となります。
したがって、遺産の2分の1は、子が取得するような内容にする必要があるといえるのです。
しかしながら、「未成年の子の養育費等を考慮すれば、その分を踏まえて、配偶者Bが遺産を取得するということにも合理性があるといえるのではないか。」との考え方もあるでしょう。
そうした考えに基づいて、たとえば子の相続分を2分の1以下にする場合には、子の取得する遺産の価額が法定相続分を満たさない相当の理由を、裁判所に説明する必要がでてきます。
(2)家庭裁判所における方針変更? ~法定相続分の確保が原則~
以前(10年くらい前)は、子の法定相続分への配慮は、それほど重要視されていませんでした。
しかしながら、最近は、この点を、裁判所がしっかりと見ている印象です。
家族の形も多様になってきましたので、子が取得すべき利益が、しっかりと確保されていることを確認する必要性が出てきたのかもしれません。
未成年者を含む遺産分割を行うにあたっては、子の法定相続分を配慮する必要があります。
5.申立て前の段階で分割方法について慎重に検討する!
以上のような理由から、次の点が重要となります。
- 特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる際には遺産分割協議書(案)を添付する必要。
(つまり相続人間で分割方法に関する合意が成立していることが前提となる。) - 遺産分割協議書(案) の内容は、未成年者の法定相続分を満たすのが原則。
- 原則を満たさない場合には、その理由を家庭裁判所に合理的に説明できないといけない。
6.特別代理人が選任された後の手続き
特別代理人が選任された後は、通常の遺産承継手続きと大きく変わるところはありません。
未成年者の代理人として、特別代理人が遺産分割協議に参加し、その合意が成立した場合には、遺産分割協議書に特別代理人が押印(実印にて)します。
法務局での不動産名義の変更、あるいは銀行等における遺産承継手続きにおいては、通常必要となる戸籍や印鑑証明書のほかに、特別代理人選任審判書と特別代理人の印鑑証明書が必要となってきます。
7.未成年者の遺産分割協議を円滑に進めるために
(1)たとえば司法書士の活用をオススメします
未成年者を含む遺産分割協議について確認してきましたが、いかがだったでしょうか?
あらためてポイントを確認すると、つぎのとおりです。
- 家庭裁判所に「特別代理人」の選任を求める必要がある可能性。
- 特別代理人の選任に際しては、「未成年者の法定相続分」を考慮する必要がある。
- 「未成年者の法定相続分」を考慮した遺産分割協議案を作成する必要性
こうしたポイントへの対応にあたっては、法律専門職によるサポートを活用することをオススメします。
とりわけ司法書士には、つぎのようなメリットがあります。
- 家庭裁判所に提出する書類の作成をサポートしてくれる。
(遺産分割協議案などの添付書類の作成代行も含む) - 特別代理人の選任だけでなく、選任後の遺産承継手続き(たとえば相続による不動産の名義変更)も見越したサポートが可能。
(2)沼津の司法書士貝原事務所のご紹介
この記事は、沼津・三島を中心に活動している司法書士貝原事務所が作成しています。
当事務所への問い合わせに関しては、つぎの記事をご参照ください。