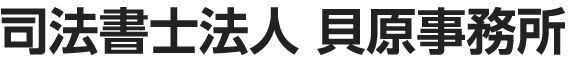目次を表示
1.死後事務委任契約とは
(1)死後事務委任契約へのニーズの高まり
死後事務委任契約とは、ご自身の死亡後の手続きを、あらかじめ第三者に委任する契約をいいます。
人が亡くなると、病院や入所施設への支払い、葬儀・埋葬の実施、自宅の物品の整理、貸家の明渡しなどなど、数多くの手続きが必要となります。
そうした、死亡後の手続きというのは、これまでであれば、子や兄弟姉妹などの親族が行ってくれていましたが、親族関係・家族関係の変化により、そういった近親者が身の回りにいない方が増加しています。
- 頼れる相続人や親族がいない
- 相続人や親族はいるけれど、いろいろな事情から、死後の事務を任せたくない(頼りたくない)
そのため、死亡後の手続きを、生前に、あらかじめ第三者に委託する契約に注目が集まっています。
(2)死後事務委任契約を利用する人はどういう人?
さきほども記載しましたが、死後事務委任契約は、つぎのような方々に利用されています。
- 相続人や親族がおらず、自身の死後の事務を執り行ってくれる人を、自分自身で探しておく必要がある方。
- 相続人や親族はいるけれど、遠方であったり、高齢であったり、死後事務という負担の多い作業を依頼することが難しい。
- 相続人や親族はいるけれど、いろいろな事情から、長年あっていない、交流がない。そのために死後の事務を依頼することはできない。
沼津市にお住いのAさん。
重い認知症のため夫Bさんは老人ホームで生活しており、いまは自宅で一人暮らしです。
お子様はいらっしゃらず、推定相続人は配偶者であるBさんに加えて、Aさんの兄弟姉妹や甥・姪となっています。
ただし、推定相続人となる人たちとは、さまざまな事情から、数十年にわたり交流がありません。
Aさん自身も健康に不安を抱えており、Aさんに万が一があったときに
『葬儀やお墓への埋葬をどうすれば良いのだろうか・・・』と悩んでいます。
死後事務委任契約は、「特定の人しか利用できない」「特定の内容を盛り込まなければならない」というものではありません。
「自身の死後事務を誰かに任せたい方」(委任者といいます。)と、「死後事務を任される方」(受任者といいます。)が、契約によって合意すれば成立するものです。
だからこそ、死後事務委任契約の締結にあたっては「誰に任せるか」「何を任せるか」「費用はどうするか」といったことを委任者自ら決めていかなければなりません。
決めるべきことと、注意すべきことについては、この記事で一緒に確認していきましょう!
(3)「死後事務委任契約」と沼津の司法書士貝原事務所
当事務所は、沼津・三島をはじめとする静岡東部地域を中心に活動する司法書士事務所です。
成年後見・任意後見のサポート、 成年後見人・任意後見人への就任も積極的におこなっており、そうした関係で「死後事務委任契約」に関する依頼も扱っています。
少子高齢化や親族関係の変化によって、「自身の死後の事務を第三者に託す必要がある」という方が増加しています。
そうした方々のご要望に応えられるよう、日々、研鑽をつんでいます。
2.「死後事務委任契約」の具体的な内容について
(1)死後事務委任契約の内容
死後事務委任契約により受任者(死後事務をまかされる人)に委任する内容は、当事者が契約により自由に決定するものです。
代表的な委任事項としては、つぎのような事柄があげられます。
- 死亡時に、施設(老人ホーム等)・病院・葬儀会社と連携を取り、ご遺体の引き取りを行う。
- 死亡届など行政に対する各種申請を行う。
- 葬儀や埋葬に関する諸手続きを代行する。
- 最後の施設利用料や入院費などの支払いを代行する。
- 借家の場合には、動産の整理・処分、借家の明渡しを代行する。
※ただし、本来は相続人が行うべき事項を含むため、とりわけ「入院費などの支払い」や「動産の整理等」については契約にあたって十分な検討が必要です。
(2)委任する事務の内容として注意すべきこと
死後事務委任契約は、ある方が亡くなった後に発生する死後の事務を、第三者に依頼するものです。
対象となる「死後の事務」は、相続や遺言に関する事柄との関係から、限定的なものになると考えられています。
(詳細は、法律学の範囲となるため、この記事では省略しますが、こういった知識が必要となることから、死後事務委任契約の締結にあたっては法律専門職(弁護士や司法書士)のサポートを受けるべきと考えます。)
たとえば、つぎのような事務は、死後事務委任契約の対象外になると考えられています。
- 特定の遺産を相続人に渡すこと(⇒遺言によるべき)
- 多額の債務を清算したり、残された不動産を売却したりすること(相続人の判断によるべき)
- 長期にわたり金銭の支出をともなう法要(三回忌や十回忌など)に対応すること
3. 「死後事務委任契約」 は誰に依頼するのが良いのか
死後事務委任契約の受任は、原則的には、法律専門職に依頼すべきと考えます。
理由はつぎのとおりです。
- 先ほども述べたように、契約の締結にあたり、法的に支障のない契約内容にすべきこと。
また、任意後見など他の法制度との関係も検討する必要があること。 - 死後の事務の事務代行費用として、多額の金銭を、受任者に対して事前に提供する必要があること。
- 死後事務委任契約の円滑な遂行のためには、死後事務に関する豊富な経験が必要であること。
(1) 成年後見(とりわけ任意後見)など関連する法制度とのつながり
理由の第1については、先ほどの項目で述べたとおりです。
相続や遺言に関する事柄との関係、成年後見(とりわけ任意後見)との関係など、関連する法制度とのつながりを処理する必要があるためです。
(2)高額の金銭をあらかじめ受任者に提供する必要がある
理由の第2は、死後事務委任契約にあたっては、死後の事務代行費用として、高額の金銭をあらかじめ受任者に提供する必要があるケースがほとんどであるということです。
死後事務を遂行するにあたっては、葬儀費用や埋葬費用を支払う必要がありますが、ご本人の預金等は、ご本人の死亡によりロックされており相続人でなければ解約ができません。
そのため、葬儀費用や埋葬費用をまかなうのに十分な金銭(場合によっては数百万円にもなります。)を、生前に受任者に提供しておくというのが、1つの方法となります。
こうして預託を受けた金銭を責任をもって管理する、管理できるという客観的な信頼が必要になってきます。
(3)死後事務に関する豊富な経験が必要となる
理由の第3は、死後事務の円滑な遂行のために、相当な事前準備が必要となるためです。
葬儀会社や埋葬先(公設墓地やお寺など)との事前調整は必須です(事前に打ち合わせをしなければ、どれくらいの費用が必要になるかも見えてきません。)。
その他にも、どういった事項を確認すべきかという点は、死後事務の経験がある人でないと難しいと思われます。
そもそも、これらの事前準備もなしに死後事務委任契約を締結したとして、はたして実際に、委任者の希望通りに死後事務が行われるのか非常に疑問です。
4.死後事務委任契約の注意点
上記で述べたように、いわゆる「おひとり様」など、死後事務委任契約を必要とする方は、近年増加傾向です。
そのため、「死後事務委任契約」を取り扱う業者が近年急増しています。
また、死後事務委任契約については、最近になって誕生した契約類型であるため、法的に未整備な面もあります。
以上の理由から、次の点に注意が必要です。
(1)身元保証契約同様に詐欺まがいの契約が増えている
老人ホームや入院に際して、身元保証人となるサービスが増加しています。
増加の理由は、死後事務委任契約の増加の理由と同様なのですが、近年、身元保証契約に起因する消費者問題(詐欺や契約トラブル)が増加しています。
トラブルが発生する構造(受任した業者を監視する人がいない等)が、身元保証と死後事務では類似しており、おそらく今後、死後事務委任契約についても、同様の消費者トラブルが増加してくると思われます。
信頼できる第三者に委任することが重要です。
(2)相続人の意向との関係
本来であれば、死亡後の事務(葬儀や埋葬。未払いの費用の支払い。)については、親族や相続人が行うべきことです。
そして、事実上、死亡後の事務を任せられる相続人はいなくとも、法律上の相続人は存在しているというケースがあります。
この場合には、一部遺産承継とも関連するため、相続人の意向にも配慮する必要があり、契約締結時、あるいは死後事務の遂行段階で注意が必要となります。
とりわけ、相続人に対して保証された「相続放棄の権利」との関係には留意する必要があります。
(3)監督者がいないため、受任者に高度の信頼性が求められる
死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなられた後に、契約の効力が発生するものです。
ましてや、相続人がいなかったり、関与が少ない場合には、受任者を監督する人がいない可能性もあります。
上記(1)で発生したトラブルの多くも、死後事務委任契約を締結する段階で高額の預り金を依頼者から受領することに起因しています。
- 死後事務委任契約の解約に応じない。
- (解約に対応しても)適切な預り金管理を行っていなかったために、預り金が返金されない。
- 依頼者の死亡後に、適切な死後事務が実行されない。
法律専門職でない個人や団体が死後事務委任契約の受任者となることを全く否定するつもりはありませんが、すくなくとも死後事務委任契約を締結しようとする段階においては、法律専門職に相談したり、サポートを依頼することが必要だと感じています。
5.死後事務委任契約の費用
具体的な内容に入る前に、誰しもが気になる「費用」について確認しておきましょう。
費用としては、制度利用にあたり必ず必要な費用(実費)と、契約締結にあたり専門家のサポートを受けたっときの費用(報酬)を分けて考える必要があります。
そして、費用のうちの大きな割合を占めるのは「専門家のサポート報酬」となります。
この点については、サポートを依頼する専門家ごとに異なるため、サポートを依頼する専門家に対して直接確認するのが一番手っ取り早いです。
- 【実費】公正証書の作成手数料
・・・2万円程度(公正証書にすることは必須ではありませんが、任意後見契約などと一緒に公正証書化することが多いです。) - 【実費】戸籍などの必要書類の収集
・・・数千円程度 - 【報酬】死後事務契約の受任を専門家に依頼
・・・依頼した専門家の報酬基準による - 【預り金】葬儀費用などに支出するための預り金
・・・50~150万円程度(※依頼内容による)
死後事務委任契約については、まだまだ受託する専門職の中でも「相場」と言えるものが形成されていないこと、葬儀や埋葬に関する希望など受託内容によって「預り金」の金額が大きく異なることから、一般的な費用感をお示しすることが難しいのが現状です。
そのため、死後事務委任契約の利用を検討している方は、契約の内容や注意点なども含めて、ぜひ法律専門職に相談してみることをお薦めいたします。