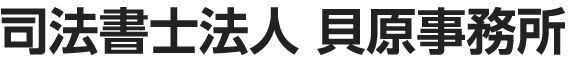目次を表示
1.おひとり様の遺産承継にはいくつかの課題
老後問題に関するご相談、相続や遺言に関するご相談を受ける中で「おひとり様」に関する悩みを良く伺います。
ここでいう「おひとり様」とは、お子様がおらず、配偶者もいない(あるいは死別した)方を指します。
- 認知症になった場合、だれに面倒を見てもらえれば良いのか。
- 自分の葬儀の準備はどのように行えば良いのか。
- 自身の財産は誰に相続されるのか。
- 相続財産を寄付したい場合には、どういった準備をすればよいのか。
こうした課題のすべてを「法律」だけが解決できるわけではありません。
しかしながら、法的な対策(いわゆる「終活」)を行うことで、ご自身の希望を満足させる解決策が見つかる可能性もあります。
この記事では、「対策しないとどうなるのか」「どういった対策があるのか」を一緒に確認していきましょう。
2.おひとり様の相続関係【なにも対策しないと・・】
(1)ご自身の兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人になるケースが多い。
誰が相続人になるかということは民法に規定がされています。
相続の第1順位は子、第2順位は直系尊属(父母や祖父母)、第3順位は兄弟姉妹となっています。
また、配偶者がいる場合には、必ず相続人となります。
おひとり様の相続においては、子供がおらず、父母等も既になくなっていることが多いため、兄弟姉妹が相続人となるケースが多くなります。
さらに、兄弟姉妹の中で、既に亡くなっている方がいる場合、代襲相続といって亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥や姪にあたる方)が相続人となります。
また、そもそも相続人に該当する人がいない場合には、相続人不存在といって、相続財産の清算手続きを行った後、最終的には国に遺産が承継されることとなります。
(2)遺産承継の希望がある場合には遺言作成を!
遺言等を作成しなければ、法律で定められた人が相続人となります。
相続人が複数いるのならば、相続人全員が遺産分割協議を行って、最終的に遺産を承継する人を決定します。
おひとり様の相続においては、遺言を作成するメリットとして、次のことが挙げられます。
- 遺産承継の希望があれば、遺言を作成することで、その希望通りの遺産承継が可能となります。
- 財産目録等を添付しておけば、せっかくの遺産が逸失してしまうことを防止できます。
- 葬儀や埋葬の希望がある場合には、付言事項をつけることで、相続人にご自身の希望を伝えることができます。
相続人に該当する方はいるものの交流がなく遺産を承継させることを希望しない場合や、相続人以外でお世話になった方に対して遺産を承継させたいという場合には、後ほどご説明するように遺言書を作成することが必要となります。
3.相続しやすい状況にする
(1)遺産承継手続きはとても大変!
前述のように、法律上定められた相続人に対して遺産を承継する場合においても、ご自身の遺産や財産を生前に整理しておく必要性があります。
遺産承継手続きは、同居していた配偶者や子が行う場合においても、非常に大変なものです。
どういった財産があるのか確認することから始まり、不動産・預貯金・株式などの財産ごとに手続きを進めていく必要があります。
ましてや、生活を共にしていなかった兄弟姉妹あるいは甥や姪が相続人となるケースでは、そもそもどういった相続財産があるのか見当もつかないということが多々あります。
(当事務所で取り扱う遺産承継業務においても、こうした理由から依頼をいただくことが多いです。)
(2)大変さを軽減できる準備を
したがって、最低限「財産目録」のようなものを残して、どういった遺産があるのか相続人に対して伝えられるような状況にしておくことが必要だと考えられます。
さらに進んで、不動産や貴重品類、お墓や仏壇など、遠縁の相続人では処分に困るようなものについては、生前にある程度整理するか、処分方法について遺言(あるいはエンディングノート)を作成することをお勧めします。
また、相続財産を明記することには問題ないものの、その後の遺産分割協議において、相続人同士が不仲であるとかあるいは疎遠であるとか、そういった場合については、やはり遺産分割協議を省略させるため遺言の作成を検討すべきでしょう。
4.遺言を残しておく
(1)遺言のメリットを確認する
今まで述べてきたように、おひとり様の相続においては、遺言書を活用することが非常に重要です。
あらためて遺言のメリットを整理すると、つぎのとおりです。
- 遺言書の中で相続財産を明記し、遺産承継手続きの対象を明示することができます。
- 遺言書の中で遺産分割方法を指定することにより、相続人全員での遺産分割協議を省略することができます。
- 遺言書の付言事項を活用することにより、残された財産の処分方法であるとか葬儀埋葬の方式だとか、遺産承継に関する希望等を相続人に伝えることができます。
(2)適式な遺言を作成する
遺言を残す際にはスムーズに遺産承継手続きが進むように、公正証書遺言で作成したり、遺言執行者をしっかりと定めておくなど、分割方法以外の事項についてもしっかりとした検討が必要です。
とりわけ「自筆証書遺言」の場合には、気軽に費用もかけずに作成できるというメリットの一方で、必要な要式を備えておらず無効となったり、記載内容が曖昧だったり不明確だったりして遺言執行に困るケースもあります。
是非とも、司法書士等の法律専門職を活用してください。
【参照記事:遺言の「ある・なし」と相続(兄弟姉妹が相続人)【比較事例】】
5.葬儀や埋葬について事前準備する
遺産に関する事項は、遺言書でカバーすることができます。
しかしながら、亡くなった後の葬儀や埋葬についても、大きな関心事でしょう。
対応策の1つめとしては、さきほどから記載しているように「遺言の付言事項」を活用する方法です。
ただし、付言事項という性質上、つぎのようなデメリットがあります。
- あくまで遺言者の希望を伝えるにすぎず、相続人等を法的に拘束する効力はない。
- 遺言が即時に発見されない場合には、付言事項を確認する前に、相続人などの近親者が葬儀・埋葬の対応をしなければならない。
対応策の2つめとしては、死後事務委任契約という契約を別途締結する方法です。
死後事務委任契約の契約を締結する人、すなわち死後事務受任者は、適任の親族がいればその形で構いませんし、親族がいなければ専門家に依頼することもできます。
現状では、馴染みのない契約かもしれませんが、今後「死後事務委任契約」はメジャーな契約になっていくことが予想されます。
死後事務委任契約の詳細については、別記事にまとめていますので、そちらをご参照ください。