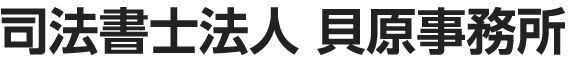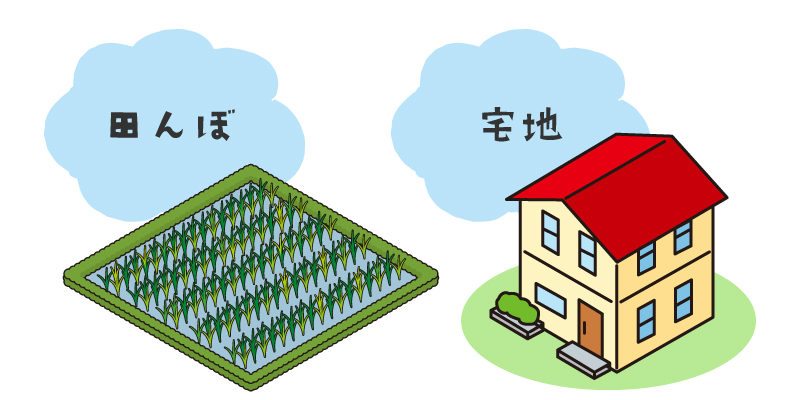目次を表示
1.土地・建物の名義人が亡くなったら?
土地・建物の名義人(登記簿上で所有権登記名義人とされている人)が亡くなった際には、その方の名義を変更する必要があります。こうした名義変更の手続きを「相続登記」といいます。
相続登記は、最終的には法務局にいくつかの書面を提出することで行います。
しかしながら、法務局に相続登記の申請をする前に、戸籍や印鑑証明書などの書類の準備や、遺産分割協議を実施し分割協議書を作成するなど、いくつもの「やっておくべきこと」が存在します。
また、遺産の承継の仕方によって、相続登記の仕方にはパターンがあります。
この記事では、相続登記の義務化や、相続登記のパターンについて確認していきます。
2.相続登記の義務化
(1)一定の期間内に「相続登記をしなければならない」ことに
令和3年4月に不動産登記法等の改正が行われ、相続登記が義務化されました。
法律が施行(変更の効力が発生すること)されるのは、令和6年4月からとなりますが、非常に大きな法律改正となりました。
改正法施行後は、不動産を所有している方について相続が発生した場合には、所定の期間内に承継者を決定し相続登記をすること、承継者の決定が難しければ「相続人申告」を行うことが義務となります。
(2)「相続人申告」制度
相続登記の義務化にあたっては、やむを得ず相続登記ができない場合に相続人が対処できるよう、「相続人申告」制度が設けられることになりました。
これは、「相続が発生しているよ」「相続人のうちの1名の連絡先はこちらだよ」という最低限の事実を申出ることによって、とりあえず義務を果たしたとみなしてもらうものです。
3.法定相続分による相続登記
相続人が複数いる場合には、遺言等で不動産の承継者が定められていない限りは、相続人間で共有された状態になります。
この共有状態は仮のものであり、相続人は遺産分割協議によって、不動産の承継者を正式に決定しなければなりません。
ただし、不動産登記法においては、仮の共有状態についても、権利保全の観点から登記をすることが認められています。これを「法定相続登記」といいます。
本来、相続登記をする際には、登記名義人となる相続人全員が登記に関与する必要があるのですが、この「法定相続登記」は相続人の1名のみからでも申請することが可能とされています。
4.遺産分割による相続登記
相続人が複数いる場合において、相続人間の遺産分割協議が成立し、不動産の承継者が正式に決定されたときには、この承継者を登記する必要があります。
不動産承継者は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を添付して、単独で相続登記の申請を行うことができます。
5.相続登記はお早めに
(1)相続登記が義務化されるから(2024年4月から)
相続登記については、先ほどご説明した通り、2023年4月から「義務化」されることとなりました。
義務化にともない、一定の期間内に相続登記がなされていない場合には、罰金を科すことができるようになっています。
相続登記の義務化と処罰の可能性を考えると、早めに相続登記をすべきというのは必然でしょう。
(2)放置すると登記手続きの難易度があがるから
くわえて、相続登記は別の理由からも早めにすべきといます。
それは、相続登記を放置することによって、資料が散逸して登記すべき不動産を失念してしまうリスクや、時間の経過によって相続関係が変化し複雑化するリスクがあるからです。
とりわけ、2点目については、数次相続の発生により、あとから遺産分割協議を行う際に非常に困難な状態になっていることが生じうるので注意が必要です。
(3)遺言による速やかな相続登記の実現
また、「相続人間で遺産分割協議がまとまらず、相続登記ができない。」という事態を回避するために、遺言の重要性が増してくるとも考えられます。
遺言において、不動産の承継者を定めておけば、相続開始後、不動産の承継者は単で相続登記を申請することができます。
【参照記事:数次相続について】
【参照記事:遺言の役割と種類について】