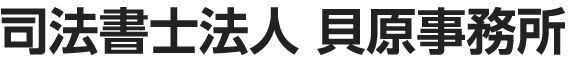目次を表示
1.相続登記についてお悩みですか?
(1)相続登記は「義務」になる!
土地や建物をお持ちの方が亡くなった際には、相続手続きの一環として、土地・建物の名義変更が必要となります(これを一般に「相続登記」といいます。)。
相続登記は、2024年4月1日から、法律によって「義務化」されます。
義務化される以上は、しっかりと手続きを進めていかなければならないものの、「相続登記」についてお悩みの方は少なくありません。
この記事では、相続による土地・建物の名義変更(相続登記)についてお困りの方に対して、多くの方が困っている・悩んでいるポイントを確認しつつ、皆様をサポートするサービス(司法書士)をご紹介します
どういった方が司法書士によるサービスを利用しているのか、相続登記の手続きに要する期間・費用についてもご案内します。
(2)相続登記について多くの方が困っている・悩んでいるポイント
- 何から手をつけていいかわからない。
- 法務局に提出する戸籍を集めるのが大変
- 相続人が複数いるが、遺産分割協議書の作成の仕方がわからない。
- 不動産だけではなく預貯金や他の遺産についても承継手続きを任せたい。
- 相続人が複数いるため、専門家に間違いのない手続きをお願いしたい。
多くの方にとって、相続登記は初めての出来事だと思います。
ですので、「相続登記」について困ったり、悩んだりするのは当然のことです。
そんなときには、是非「専門家」を頼ってみてください。
でも「相続登記の専門家って誰なの?」と更に悩みが増えてしまったかもしれません。
その悩みに対しては、ズバリの答えがあります。
相続登記の専門家は「司法書士」です。
2.悩みや困りごとの解決のために司法書士の活用を!
ひとくちに「相続登記」といっても、皆さまが悩まれているポイントは様々です。
それに対して、相続登記の専門家である司法書士は、つぎのようなサービスを提供して、皆さまの課題解決をサポートしています。
(1)相続登記をスムーズに進めるためのサポート
- 相続登記に関する手続き全般をサポートする(面倒な戸籍集めも任せられる)
司法書士は「登記」の専門家です。
そして相続登記の申請だけでなく、戸籍などの必要書類の収集、相続人が用意すべき書類の作成(その代表が遺産分割協議書です。)にも対応しています。
【参照記事:相続登記の手続きの流れ】
- 相続関係の確定をサポートする(法定相続情報一覧図の作成)
相続登記の申請にあたっては、必要な戸籍を集めて、相続人を確定させる作業が必要となります。
この戸籍収集は、①戸籍を読み解く必要があること、②場合によっては遠方の市町の役所に請求をする必要があること、から非常に手間のかかる作業となっています。
この点については、法務局による「法定相続情報証明制度」を活用するのが有効であり、この制度の利用と、それにともなう必要書類の取得代行をサポートすることが可能です。
【参照記事:法定相続情報証明制度について】
- 遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合には、原則として「誰が土地・建物の名義を承継するのか」を相続人全員の協議によって定める必要があります。
これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議を行い、特定の相続人(たとえば長女)が不動産を取得すると決定した場合には、これを書面にまとめ、相続人全員が実印による押印を行います。
こうして作成されるのが「遺産分割協議書」です。
相続登記の申請に際しては、この遺産分割協議書の添付が必要となっています。
司法書士は、相続登記に添付する遺産分割協議書の作成をサポートしています。
(また、遺産分割協議書は、相続登記だけでなく、預貯金などの遺産承継手続きにも活用できます。)
- 相続登記の申請を代理する
相続登記の申請は、不動産(土地・建物)の所在地を管轄する法務局に対して行います。
たとえば、沼津市や三島市の不動産に関する相続時申請は静岡地方法務局沼津支局に行います。富士市に関する申請は富士支局に、下田市に関する申請は下田支局ということになっています。
申請にあたっては、申請書のほか、戸籍(または法定相続情報一覧図)・遺産分割協議書・印鑑証明書など所定の書類を添付する必要があります。
司法書士は、申請書の作成や、添付書類の収集・作成をサポートしています。
- 遺産承継サポート
これまでは、相続による不動産の名義変更(相続登記)を中心にご案内してきましたが、相続による遺産承継手続きが必要となるのは、不動産に限りません。
不動産のほかにも、預貯金・上場株式・投資信託など様々な「遺産」があります。
これらの遺産を相続人が承継する手続きを司法書士はサポートしています(遺産整理業務とか遺産承継業務などといわれています。)。
(2)「沼津の司法書士貝原事務所」のご紹介
当事務所は、2名の司法書士(うち1名は行政書士を兼業)が所属する司法書士法人です。
沼津・三島をはじめとする静岡県東部を中心に司法書士サービスを提供しています。
司法書士は「不動産登記の専門家」ですが「預貯金などの相続」や「相続登記に関連するサポート」も行っています。
3.どういった人が相続登記のサポートを利用しているの?
司法書士は、以上のような相続登記のサポートを業務として提供しています。
業務である以上は、お客様から報酬をいただいてサービスを提供しているのですが、「お金を払ってまで相続登記のサポートを依頼する人」には、どういった方が多いのでしょうか。
パターンとして多いのは、つぎのような方です。
- 手続きにかかる時間を短縮したい
相続登記などの遺産承継手続きを行わなければいけないけれど、法務局や銀行が開いているのは平日の日中のみです。
平日は仕事があるから、手続きに時間をかけているのは難しいよ、という方からご依頼いただくケースがあります。
- 正確に実施したい
ひとくちに相続登記といっても、申請にあたっての準備(相続関係の確認、対象不動産の洗い出し、遺産分割協議書の作成)など、さまざまな作業が必要となってきます。
そこには、行政サービスに関する知識(戸籍の読解や名寄帳の取得など)、登記申請に関する知識、相続に関する法的知識が必要となってきます。
司法書士は、それらの専門知識とともに「相続登記の申請」をサポートしています。
- 遺産承継手続きを丸ごと任せてしまいたい
相続手続きをおこなうべき遺産は、不動産だけではありません。預貯金・上場株式・投資信託など様々な「遺産」があり、それぞれについて遺産承継の手続きが必要となります。
そうした遺産承継の手続きを、一括して任せてしまいたいというお客様もいらっしゃいます。
4.相続登記に要する「時間」「費用」
(1)期間について
相続登記に要する期間としては、必要な作業を大きく2つにわけることができます。
- 申請に必要な書類を準備する時間(相続関係によって様々)
- 申請の処理に必要な時間(おおむね2週間程度)
「必要な書類を準備する時間」には、戸籍集めや遺産分割協議の実施など、相続関係や相続人の都合によって時間が伸びたり短くなったりするものが含まれます。
あくまで「目安」となりますが、受任から登記申請までの期間は次のとおりです。
| 【ご依頼の概要】 | 手続き完了までの期間(目安) |
| お父さんが亡くなり、相続人が母と子供2名。 母は沼津に住んでいるが、子供は遠方に居住している。 | 2~3カ月くらい |
| 相続人は2名。 2人とも沼津市内に居住していて書類集めや押印作業もすぐにできる | 1~2カ月くらい |
| 相続登記を数代にわたって放置していた。 戸籍で調べたら、相続人が20名いた。 | 1年以上かかることも・・ |
3番目のケースについては、「相続人が20人もいるの!」と驚かれるかもしれません。
しかしながら、こうした案件も、司法書士にとっては特別なものではありません。
(2)費用について
相続登記に要する費用としては、つぎの3つに分類することができます。
うえの2つは、ご自身で手続きを行った場合にも必要となる費用です。
一番下の「司法書士報酬」は、司法書士に相続登記のサポートを依頼した場合に限り、発生する費用です。
(ご自分で相続登記の手続きを進める場合にはかかりません。)
| 費用の種類 | 内容 |
| 登録免許税 | 登録免許税は登記に際して法務局に収める税金です。 相続登記を行う土地・建物の固定資産税評価額に0.4%をかけた金額となります。(※1) たとえば、土地・建物の固定資産税評価額が2000万円の場合、登録免許税は8万円ということになります(2000万円×0.4%) |
| その他実費 | 一例として次のようなものがあげられます。 (1)戸籍を取得するための手数料、郵送費用 (2)登記の状況を確認するための登記情報の取得費用など |
| 司法書士報酬 | 司法書士事務所によって異なります。 また、相続登記といっても、具体的な事案によって作業量(報酬額)は異なります。 一般的には、取り扱う不動産(土地・建物)の数が多かったり、関与する相続人の人数が多かったりすると、それにともない報酬も増えていきます。(※2) |
※1 登録免許税については、免税規定があります。
※2 当事務所の報酬については、モデルケースをご用意して説明していますので、つぎの参照記事もご覧いただければと思います。
【参照記事:相続登記の報酬モデルケース(家族内での相続)】