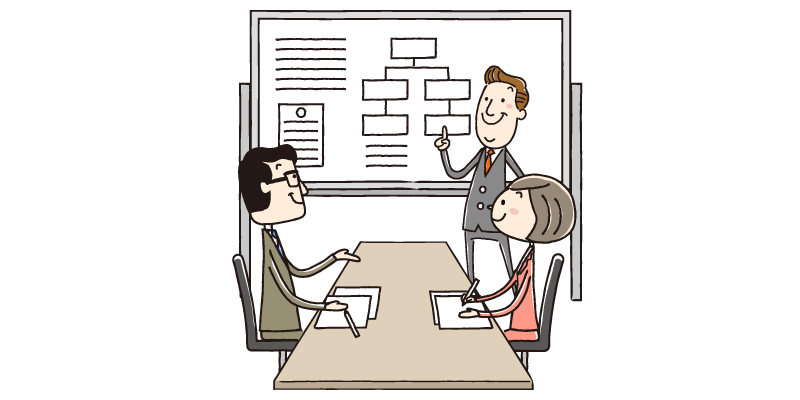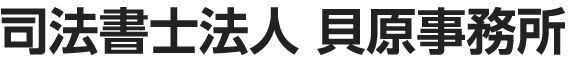目次を表示
1.成年後見制度とは(法定後見と任意後見)
(1)法定後見と任意後見の区別
成年後見制度は、認知症等によって法的な判断能力が不十分な状態にある方に対して、法律的な側面からサポートする人を選任する制度です。
成年後見制度において、サポートを受ける人を「ご本人」、サポートする人を「後見人」等といいます。
また、成年後見制度は大きく2つの仕組みにわかれます。
- 法定後見:
サポートが必要な方に対して、裁判所がサポートの範囲(権限)やサポーター(成年後見人等)を選任する仕組み - 任意後見:
将来的に法的な判断能力が不十分な状態となることに備えて、ご本人とサポーター候補者が契約を締結する仕組み。サポート範囲も契約によって定めらる。ご本人の法的な判断能力が不十分な状態となってはじめて、サポーターの権限は発動する。
この記事では、法定後見(家庭裁判所が後見人を選ぶ)にフォーカスをあてて解説していきます。
任意後見(事前に契約によって後見人を選ぶ)に興味がある方は、つぎの記事をご覧ください。
【参照記事:任意後見契約について】
また、法定後見は、サポーターの権限の範囲によって、後見・保佐・補助と呼び方が分かれてきます。
【参照記事:法定後見の3類型について】
この記事では、説明を簡単にするため、「後見」類型を前提とした内容になっています。
そのため、次項以下では、たんに「後見制度」と記載した場合には「法定後見のうち後見類型」を指しますのでご留意ください。
(2)後見人を活用すべきモデルケース
成年後見制度に関する、具体的な説明にうつる前に、「どういったケースで成年後見制度を活用するのか」、モデルケースを確認しておきましょう。
たとえば、つぎのようなケースでは、成年後見制度の利用を検討するべきです。
【モデルケース1:母の自宅(空き家)を売却して、お金にかえたい。】
沼津市に在住のAさん。
母Bさんのことで悩みがあった。母Bさんは、父Cさんの死後、自宅で一人暮らしをしていた。
父Cさんの死から数年たったころ、母Bさんに認知症の症状がではじめた。認知症の症状は少しずつ悪化し、一人暮らしが難しくなったため、老人ホームに移ることになった。
母Bさんの自宅は空き家となった。
空家となった自宅は固定資産税などの管理費がかさむうえ、老人ホームの施設利用料を考えると、空き家を売却して現金に換えたい。ところが、空き家の所有者である母Bさんは認知症であるため、「売買取引(売買契約)ができない」と不動産屋に断られてしまった。
【モデルケース2:叔父(叔母)の生活サポート・財産管理をする人をみつけたい。】
三島市に在住のAさん。
叔父Bさんのことで悩みがあった。叔父Bさんは、わけあって一人暮らしをしており、生活をサポートしてくれる親族が身近にいない。
Aさんは、Aさんの父Cさんが亡くなってからは、叔父Bさんとは疎遠になっている。
比較的近くには住んでいるので、顔を合わせることはあったが、あいさつ程度であった。ある日、叔父Bさんの見守りをしていた地域包括支援センターの相談員Dさんから、Aさんは連絡を受けた。
聞くと「叔父Bさんの認知症の症状が悪化し、自宅での生活は困難になった。ついては、特別養護老人ホームに入所したいので、手続きを手伝ってほしい。」とのこと。Aさんとしても、親族ではあるからできる限りのことはしたいとは思うものの、仕事や子育てで忙しくサポートにも限界がある。
ましてや、叔父とはいえ、お金の管理や施設入所の身元保証には抵抗がある。
2.後見人には何が求められているのか(後見人の権限・職務)
いよいよ、成年後見制度の具体的な説明に入っていきます。
すこし堅苦しい話になりますが、成年後見制度の利用を検討するにあたっては、知っておきたい事柄です。
どうしても眠くなってしまうという方は、「(3)後見人の権限」にジャンプしてください。
(1)成年後見制度の理念
成年後見制度の理念として、つぎの3つが挙げられます。
- 自己決定の尊重
- 現有能力の活用
- ノーマライゼーション(みんなが等しく社会のおいて生活できる環境を実現する)
特に注意したいのは、“「後見」=「認知症」=「判断能力がない」=「後見人が何でも決められる!」”という誤った考えです。
上記の3つの理念を理解したうえで、ご本人の意思を汲み取り、ご本人の意思を尊重して、後見人としての権限を活用していく必要があるのです。
(2)後見人に求められていること
後見人に求められているのは、自らの法的な権限を活用して、ご本人の生活全般をサポートしていくことです。
「サポート」というのは、ご本人が望むであろう生活の質を維持したり、ご本人の状態に合わせた生活状況の改善を行うことです。
そうしてみると、「モデルケース2」(叔父の生活サポート・財産管理をする人をみつけたい)においては、後見制度を利用したい人と、後見人に求められている役割がマッチしていることになります。
一方で、「モデルケース1」(母の自宅を売却したい)では、後見制度を利用したい人のニーズとは少し食い違いがあることになります。
この点は、後見制度の利用にあたって、注意しなければならない点となります。
(3)後見人の職務(身上保護・財産管理)
そして、後見人としての職務は、大きく2つに分かれます。
「身上保護」と「財産管理」です。
「身上保護」とは
身上保護とは、ご本人の生活環境を整備する職務であり、たとえば次のようなものが該当します。
- 医療に関する事項
- 介護に関する事項
- 住居の確保に関する事項
- 病院や施設の入退所や処遇のチェックに関する事項
「財産管理」とは
財産管理とは、ご本人の財産の管理や処分をおこなう職務であり、たとえば次のようなものが該当します。
- 不動産や預貯金の管理・処分に関する事項
- 家賃・入院費・施設利用料など日常生活にかかる支出の管理に関する事項
- 年金などの給付金の請求・受領に関する事項
- 相続(とりわけ放棄や遺産分割)に関する事項
後見人は、これらの職務を、法的な代理権を活用しておこなっていきます。
そのため、次のような事がらは、後見人の権限の範囲外とされます。
事実行為
たとえば「ご本人を介護すること」「ご本人の代わりに食料品の買い物に行くこと」など、多くの方が「生活のサポート」と聞いて、すぐに思い浮かべることは、じつは後見人の職務の対象ではないのです。
後見人は、「介護サービス」や「買い物代行サービス」などを提供する事業者と、ご本人の代わりに「契約」して、ご本人の生活をサポートしていくのです。
他人が代理して決めるべきではない事柄
よく例に挙げられるのが、つぎの2つです。
- 婚姻や養子縁組など「身分行為」といわれる意思決定
- 医療に関する意思決定(たとえば外科手術。胃ろうや経管栄養など。)
とくに「医療に関する意思決定」は、成年後見制度の利用者となる方の多くが高齢者であり、医療と関係するシーンが多いので、後見人としては非常に苦労するところです。
3.後見制度の利用方法
(1)法定後見の利用は「家庭裁判所への申立て」からスタート
法定後見の利用は、ご本人の住所地の家庭裁判所に、「ご本人のために後見人等を選任してください」と申立てをすることでスタートします。
申立てをすることができるのは、ご本人や親族(4親等以内。子や甥・姪は含まれます。)など限定されています。
(2)家庭裁判所への申立てに必要な書類
家庭裁判所に申立てをする際には、添付が必要な書類がいくつかあります。
詳細は省略しますが、とくに重要なのが「医師の診断書」と「推定相続人の同意書」です。
- 医師の診断書:類型(後見・保佐・補助)の判断をする際の重要資料。
- 推定相続人の同意書:親族が後見人になることを希望する場合には重要に。
このほか、申立てについて詳しく知りたい方は、つぎの記事もご参照ください。
(3)「成年後見人等候補者」の記入
また、家庭裁判所に申立てをする際には、「後見人等候補者」を家庭裁判所に伝えることができます。
あくまで、誰を後見人にするか(そもそも類型をどうするのかも含めて)は、家庭裁判所が決定することです。
ただし、とりわけ親族が後見人になることを希望するケースにおいては、「後見人等候補者」欄に親族の名前が記載されているときにかぎり、その記載された候補者が適任であるか否かを検討するとされています。
4.後見制度の利用に伴うお金(費用)
後見制度の利用に際しては、次のような費用が掛かってきます。
- 家庭裁判所への申立てにともない必要となる費用
- 後見人への報酬
(1)家庭裁判所への申立てにともない必要となる費用
後見開始申立てにあたり、家庭裁判所に納める費用は、だいたい1万円くらいです。
このほかに次のような費用がかかってきます。
- 医師の診断書作成料
5000円~1万円くらいのところが多いです。ただし病院により様々。 - 戸籍等の公的証明書の取得費用(数千円)
このほか、家庭裁判所の審理の中で「鑑定」が求められる場合には鑑定費用、司法書士等に申立てのサポートを依頼した場合には司法書士等への報酬が必要となってきます。
(2)後見人への報酬
後見人は、家庭裁判所に申し立てることによって、後見人の職務に対する報酬を受領することができます。
後見人の報酬について、押さえておきたいポイントは、つぎの3つです。
- 後見人の報酬を負担するのは、ご本人の財産のみであること。
- 後見人の報酬額を決めるのは、家庭裁判所であること。
- 報酬の申立てをしなければ無報酬となること(とりわけ親族が後見人となるケース)
専門職といわれる人が後見人になるケースでは、原則として、後見報酬が発生してきます。
専門職の後見報酬については、つぎの記事をご参照ください。
【参照記事:専門職後見人の報酬について】
5.制度利用のポイント
(1)メリット・デメリットを事前に知ること!
成年後見制度は、法律によって仕組みが定められている制度です。
したがって、具体的な事案に対して、非常に効果的な場合もあれば、逆に、使い勝手が悪いと感じる面もあります。
注意すべきなのは、皆さんが成年後見制度を利用するにあたって、制度のメリットやデメリットを正確に把握した上で、利用に向かうと言うことです。
とりわけ、成年後見制度は利用を途中で中止することが、原則的にはできない仕組みとなっています。
申し立てをしてから、こんなはずじゃなかった、こんなことになるとは思ってもいなかった、と言うようなことがないように、事前に制度をしっかりと把握してから申し立てに進みましょう。
よく耳にするメリット・デメリットはつぎのとおりです。
- 【メリット】
〇 家庭裁判所の監督のもと、ご本人の財産が守られる。
〇 介護も含めた生活基盤をつくる・ささえる仕組みを後見人が用意してくれる。 - 【デメリット】
〇 専門職が後見人や監督人となった場合には、専門職に対する報酬が発生する。
〇 不動産売却や遺産分割など、特定の課題解決のために後見制度の利用を開始したケースにおいても、その課題が解決したからといって後見制度の利用を止めることができない。
ただし、これらのメリット・デメリットは、具体的な事案においては、逆の意味にもなります。
ご本人にとっては、後見制度が「家庭裁判所も含めた後見人による過度な生活への介入」と感じられることもあるでしょう。
一方で、司法書士などの専門職が関与することで、ご本人や親族にとって、間違いなくプラスになることもあります(判断能力の低下で逸失していた財産の回復。不動産売却や遺産分割など、法的な課題をスムーズに解決するなど。)。
結局のところ、ご本人やご親族が直面する具体的な課題に対して、成年後見制度の利用が適しているのかを、個別に判断していくしかないのです。
そして、後見制度に関する知識や経験のある専門家への相談は、その判断を適切なものとする手助けとなるはずです。
(2)当事務所の紹介
当事務所は、沼津市三島市などの静岡県東部地域を中心に司法書士として法務サービスを提供しています。
成年後見制度との関連では、つぎのような業務を行っています。
- 制度利用開始時の裁判所への申し立て書類のサポート
- 親族後見人の後見業務のサポート
- 後見人等への就任。
とりわけ、実際に後見人に就任し後見人として活動を行う中で学んだこと・感じたことは、その他の業務を行う場面でも、非常に参考となっています。
そうした経験知を発信することにも積極的に取り組んでいます。
この記事に関連する記事