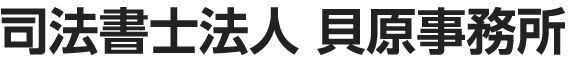目次を表示
(はじめに)相続放棄の要否
「遺産の分け方」を考える前に、相続放棄の要否を検討する必要があります。
親族関係等の理由で「心情的に相続したくない」「遺産を受け取るつもりもないし遺産分割協議に関与したくない。」という場合には、遺産分割に関与することなく、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをとれば良いでしょう。
一方で、「マイナスの財産が多いようであれば相続放棄をしたい」というようなケースでは、前提として遺産調査が必要になります。
相続放棄については、原則として、相続の事実をしってから3カ月以内に家庭裁判所に対して申述しなければなりませんので、時期的な制限には注意しなければなりません。
1.各相続人の承継割合について
(1)法定相続分に拘束される必要はなし!
民法の中では、「法定相続分」と言って、とりあえずの相続人の取得割合が決められています。
これは、相続人間での協議がまとまらない場合(とくに裁判所における調停や審判)において分割割合の基準として利用されるもので、相続人全員が合意できるのであれば、法定相続分にこだわる必要は全くありません。
各人が納得さえすれば、1人の相続人が総取りしても、相続人全員で平等に分け合っても良いのです。
(2)遺産の受け取り方はさまざま
また、具体的な遺産の受け取り方にも、遺産そのものを受け取る方法(現物分割)、不動産等を現金に変えて受領する方法(換価分割)、遺産を受け取る代わりに金銭債務を負担し公平を図る方法(代償分割)などがあります。
- 現物分割:遺産そのものをわける
- 換価分割:お金に換えてわける
- 代償分割:遺産を受け取る代わりにお金を払う。
これらの方法の選択も、法律上で決まっているわけではないので、相続人が自由に選択することができるのです。
たとえば、つぎのような分け方も可能です。
- 不動産は、相続人Aが取得する。
- Aは、その代償として100万円を相続人Bに支払う。
- 預貯金500万円は、Aが40%、Bが60%となるような割合で分割する。
2.相続税申告の要否を検討
遺産の分け方を考える前に、まずは相続税申告の要否を確認する必要があります。
仮に、相続税申告が必要となる場合には、分け方によって相続税課税の有無や、相続税の金額が変わってくるからです。
課税のことだけを考えて、将来的な財産活用の検討を全くしないことは論外ですが、課税されない分け方があるにもかかわらず、それを全く考慮しないというのもおかしな話でしょう。
相続税の申告が必要な場合には、早い段階で税理士さんに相談して、税務上のメリットを享受することを念頭に置きながら、分け方を検討すべきではないでしょうか。
3.検討すべき順序(分割しにくい不動産から)
相続財産の種類ごとに考えてみると、まずは分割しにくいものから検討するべきです。
分割しにくいもの(代表例が不動産)を承継する人を決めて、あとは分割しやすい財産(たとえば預貯金)で相続分の調整を図るのがスムーズです。
分割しにくいものとしては、前述のような不動産が代表例ですし、その他にも自動車や自社株などがあげられます(自社株は、形式的には分割しやすいものですが、経営面を考えると安易に分散させるわけにもいかないので、分割しにくいものに分類しています。)。
4.遺産分割における「不動産」について
(1)ポイントとなるのは「不動産」
遺産分割において、ポイントになるのは不動産ではないでしょうか。
昔は、財産的価値が高いために、相続人がこぞって承継を希望し、争いの原因となりました。
ところが、現在では、管理や税金の負担が嫌われて、相続人間で押し付けあう結果、協議がまとまらない原因となることも多いです。こうした不動産は「負動産」とも呼ばれています。
そんな不動産ですが、相続人間で承継先を決定できない場合に、「とりあえず共有」ということで、相続人全員で法定相続分の割合で登記される方もいらっしゃいます。
様々な事情はあるかと思いますが、司法書士の立場からは「とりあえず共有」は絶対に避けるべきと考えます。
(2)不動産の「とりあえず共有」は避ける!!
共有する際には、管理の仕方や管理費の負担など、不動産にまつわる様々な負担について、その分担方法を決めなければなりません。
「とりあえず共有」のパターンでは、これらの負担方法を決定していないため、共有後に、共有者間でトラブルになることがあります。
さらに、いざ不動産を処分したい場合には、共有者全員の合意が整わなければ処分することができません。
にもかかわらず、共有者間のトラブルのために処分もできないという事態になりがちです。
司法書士業務を行う中で、安易な共有を選択した結果、その後に不動産トラブルが発生したケースや、共有関係の解消のために多額の費用をかけることになったケースを山ほど見てきています。
(3)まずは「単独所有」する方向で検討する
したがって、不動産は極力単独所有にすること。
単独所有による不公平感が出るのであれば、他の財産の分割方法で調整するか、代償金の支払いを行う(不動産を承継するかわりに金銭を支払う)などして調整するのが良いと考えます。
共有が推奨されるケースとしては、直近で不動産を売却し、その売却益を分配したいとき(換価分割)を選択するときです。
その他にも、税務上の観点から、上記のような共有のリスクを理解したうえで、共有を選択するケースもあります。
なお、自宅不動産については、特に配偶者の方について、配偶者居住権という制度が作られました。これを利用すれば、所有者は子供としつつ、引き続き当該不動産で生活を送る配偶者のために利用権を設定することができます。
【参考記事:配偶者居住権について】
5.遺産分割における「上場株式・投資信託」について
これらは比較的分割しやすい財産なので、さほど困ることはないかと思います。
注意したい点としては、売却して現金を相続したい場合の手続きです。
上場株式や投資信託については、いったん承継者の口座を開設し、そこに承継する株式等を移管する必要があります。
直接売却してお金を受け取るということはできません。
売却する場合には、移管した後に、承継者名義で売却する必要があります(そして、売却益が出た場合には課税がなされます。)。
ですので、Aさんが代表して上場株式等を承継し、自らの口座で売却した場合(かつ売却によって利益が生じた場合)には、Aさんに対して所得税等が課税されることになります。
その課税を踏まえて、相続人間で分割割合を検討していれば良いのですが、課税のことを忘れて分割方法を決定していると、Aさんだけ課税負担分、受け取る金額が少なくなってしまうので注意が必要です。
もちろん、各相続人が希望する割合で承継し、各人で売却すれば、各人が税金を納めることになるので、そのような不都合は生じません。
6.遺産分割における「預貯金」について
(1)預貯金は複数の金融機関にあるのが通常
預貯金については、分割しやすい財産ですし、不動産のように受け取った後の管理が問題になるということもありませんので、「どのような割合で承継するか」ということで困ることはないでしょう。
わけやすい財産の代表格である「預貯金」ですが、いっぽうで「複数の金融機関に分散しがち」というマイナスの側面もあります。
3つの金融機関に口座が分散していると、それぞれ3つの金融機関で相続の手続きをしなければなりません。
また、預貯金全体を3等分にわけたいけれど、預貯金口座が複数の金融機関に点在しているときには、どう対応すれば良いのでしょうか?
(2)複数ある口座を効率的に解約する方法
技術的な話になりますが、複数の金融機関に口座がある場合において、遺産承継手続きの負担を減らすコツとして、次のような方法があります。
相続人として甲・乙・丙の3名。
A銀行(180万円)、B銀行(70万円)、C銀行(50万円)に預金(合計300万円)があるとします。
そんなときには、次の1または2、いずれかの方法をとると、事後の承継手続きが簡便になります。
- A B C銀行の預貯金の合計を3等分して相続する。
分配については、甲を代表相続人とし、甲が代表して預貯金の解約手続きを行うものとする。
甲は、解約した預金を、いったん自分の口座にプールする。
その後、甲から、乙・丙に100万円ずつ分配する。 - A B C銀行の預貯金については、甲が全て相続する。
甲は預貯金を相続する代償として、乙・丙に対して各100万円を支払う。
このような記載をするメリットとしては、銀行所定の書式に押印するものを甲だけに限定できるというものです。
A・B・Cの預貯金をそれぞれ3等分して、甲・乙・丙それぞれで受け取ることにすると、3行すべての承継手続きで、相続人全員の押印が必要となります。
手続き負担を省略するために、上記の方法を選択します。
なお、ゆうちょ銀行のように、遺産承継手続きを強制的に上記1の方法で指定してくる銀行もありますのでご留意ください(この場合には、代表相続人から各相続人への分配の作業が必須となります。)。
7.司法書士による遺産承継手続きのサポート
ここまで、相続した資産の種別ごとに、分け方のポイントを確認してきました。
- 「意外と考えなければいけないことが多い・・」
- 「ひとつひとつの手続きは簡単そうだけど、複数の手続きを進めていくのは大変そう・・」
こういった感想を持った方もいるかもしれません。
そうした方には、司法書士による遺産承継サポートの活用をご提案します。
遺産相続の手続きは、相続人自らが進められるものですが、最近では、つぎのような事情で専門家による遺産承継サポートを利用する方が増加しています。
- 亡くなった方との関係性が薄く、相続人が相続財産を把握していないケース。
- 相続手続きを進める時間的な余裕がないケース
- 複雑な相続手続きを、専門家(司法書士)に丸投げしたいケース
司法書士による遺産承継サポートについては、つぎのような記事を作成しています。
こちらも、ぜひご参照ください。