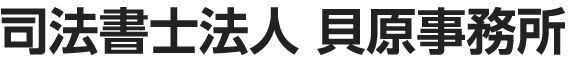目次を表示
1.相続登記って?
(1)相続登記とは
相続登記とは、亡くなられた方(被相続人といいます。)が所有していた不動産の名義を、その不動産を引き継ぐ相続人の名義に変更する手続きのことをいいます。
ひとくちに相続登記といっても、さまざまなパターンがあるのですが、この記事ではシンプルなパターン(相続人同士の話合いで不動産を承継する人を決める)を前提として相続登記の進め方をご紹介していきます。
(2)相続登記の流れ
最初に、相続登記の全体像を確認しておきましょう。
- 戸籍集めによる相続人の確定
- 相続登記をすべき不動産の調査
- 相続人同士で不動産を取得する人を決定(遺産分割協議)
- 相続登記を法務局に申請(必要書類とともに)
当事務所では、相続登記のご案内をする際に、以上のような「4つのステップ」に分解して、ご説明しています。
(3)相続登記についての関連記事
このあと、相続登記をすべき「不動産(土地・建物)」を確認するための方法について、解説していきます。
さきほどの「相続登記の4つのステップ」については、つぎのように記事をわけてご説明していますので、他の項目にご興味があれば、こちらも見ていただけると、うれしいです。
2.相続登記をすべき不動産はどれだ!
(1)相続登記すべき不動産を自分自身で確認する必要がある!
相続登記の申請は、「この土地・建物について、所有者の名義を変更してください。」という書面を法務局に提出することでおこないます。
相続による名義変更をする「土地」や「建物」を、相続登記の申請先である法務局が勝手に調べてくれるわけではありません。
あくまで申請をする側で「この土地とこの建物を相続しました!」と指定しなければならないのです。
(2)相続の対象となる不動産を漏らさないことが重要
そのため、相続登記をすべき土地・建物を、相続登記を申請する際に漏らしてしまうと、相続登記がなされないまま放置されることになってしまうのです。
放置された結果、将来「ご先祖名義の相続登記」という、非常に難しい相続登記をしなければならない可能性もあります。
【参照記事:複雑な相続登記(ご先祖名義の土地の相続登記について)】
相続登記の申請にあたって、相続の対象となる土地や建物の確認は、とても大切です。
3.相続登記をすべき不動産の確認方法
それでは、相続登記をすべき不動産(土地・建物)は、どのように確認していけば良いのでしょうか?
ここでは、代表的な3つの方法を、ご紹介します。
(1)固定資産税納税通知書を見てみる
まずは、固定資産税納税通知書です。
毎年4月~5月に、土地・建物の所在する市町から送付されてくるものです。
沼津市の場合「固定資産税・都市計画税納税通知書」として送付されてきます。
そのなかの、「課税明細書」の部分を確認すると、固定資産税の課税されている土地や建物が記載されています。
注意点は、つぎのとおりです。
- 固定資産税が課税されない物件が掲載されないケースがある。
- 共有不動産の場合には、代表者名義で送付がされてくるため、他の共有者を見落とす可能性がある。
(A・B共有の不動産について、通知書が「Aその他」のような形で送付されてきて、B名義を見落とす。)
(2)名寄帳という書類を取得する【オススメ!】
名寄帳とは、簡単にいえば、ある人がある市町において所有する土地・建物の一覧表です。
市町によって正確な呼び名が異なるのですが、沼津市では「沼津市固定資産税課税台帳兼名寄帳」と呼ばれています。
その市町内の土地・建物(正確には固定資産)を所有者ごとに一覧にしたもので、各市町の資産税課などで申請をすると取得することができます。
注意点としては、2つあります。
- 市町ごとに発行されるものなので、沼津市と長泉町に不動産を所有されている方の名寄帳を取得したい場合には、沼津市と長泉町の両方に、名寄帳の交付申請をしなければならない。
- 市町によっては、「非課税物件は掲載しない」「共有不動産の場合、筆頭者の名義でしか名寄せされない。」など特殊なルールで運営しているところもある。
以上のような注意点はありますが、比較的簡単に取得できるうえに、相続登記に必要な情報を漏れなく確認できることから取得をオススメするものです。
(3)保存してある権利証(登記済証や登記識別情報)
ご自宅等で保存している土地・建物の権利証(登記済証や登記識別情報)を確認して、過去に売買等によって取得した物件や、相続により取得した物件を確認していく方法です。
遠方の市町の、固定資産税が課税されていない不動産の場合だと、こうした方法で見つけられることが多いです。
ただし、多くの方にとっては見慣れた書類ではないので、関係ない権利証を見ていたりとか、記載されている物件を見落としてしまうということも、可能性としてはあります。
(4)調査結果をもとに登記事項証明書や登記情報を取得する
ここまで3つの方法を紹介してきましたが、いずれも一長一短あり「これを確認しておけば100%大丈夫」という方法がない点は、知っておいていただきたいです。
これらの方法によって、相続登記をすべき不動産が確認できたら、その不動産の登記事項証明書や登記情報を取得し、土地や建物の登記の内容をチェックしましょう。
登記事項証明書は、法務局が発行する公的な証明書です。
登記情報は、インターネットで簡単に取得できるものです(公的証明書ではありませんが、相続登記に利用する分には問題ありません。)。
遺産分割協議書や相続登記の申請書の作成にあたっては、上記の課税通知や登記されている情報をもとに「土地・建物」を特定していく必要があります。
4.相続登記や対象不動産の確認は自分でできる?
専門家に依頼をするなら?
(1)相続登記・対象不動産の確認は自分でできる
相続登記や対象不動産の確認は、専門家に依頼せずとも、ご自身でおこなうことができます。
固定資産税の納税通知書が手元にない場合には、市町の資産税課において、名寄帳を取得することもできます。
相続人が、亡くなられた方の名寄帳を取得する場合には、戸籍など相続関係を証明する書類の提示を求められるのが原則です。
【参照記事:名寄帳(なよせちょう)の相続手続きへの活用】
ご自身で市役所・町役場に行かれる場合には、電話などで、必要書類を事前確認すると良いでしょう。
(2)相続登記すべき不動産の見落としに注意!
とはいえ、土地・建物の調査には、すこし専門的な知識が必要となります。
- 自宅の敷地は1つの土地だと思っていたら、登記上は2つの土地だった。
- 自宅の敷地に出入りするための私道に、亡くなった方の名義が入っていた。
- 相続人が把握していなかった田・畑・山林などがあった。
相続登記を申請する際に、ほんらい登記すべき土地や建物を漏らしてしまっても、法務局は指摘をしてくれません。
(3)相続登記の専門家は司法書士
司法書士は、相続登記を始めとした登記を専門的に扱う職業です。
相続登記と簡単に言っても、対象となる不動産(土地・建物)や、相続関係・親族関係はさまざまです。
「自分で調べてみたけれど、ちょっと難しいかもしれない」「自分で手続きをするのは不安だから、専門家(司法書士)に任せたい。」という場合には、ぜひお近くの司法書士にお声がけください。
5.相続登記を任せるなら司法書士に!
(1)沼津や三島などの沼津近隣の方なら
「知っている司法書士がいる!」「過去に司法書士に依頼したことがある!」のならば、ぜひ、その司法書士に「相続登記について相談」してみてください。
沼津や、三島市などの沼津近隣にお住まいの方で、そうした司法書士がいないということであれば、ぜひもと当事務所(沼津の司法書士貝原事務所)にお声がけください。
(2)身近な司法書士の探し方
「沼津近辺には住んでいない」「沼津在住だが、いろいろな司法書士を検討したい。」ということであれば、つぎのサイトで身近な司法書士をさがしてみましょう。
当事務所は、静岡県沼津市にあるため「静岡県司法書士会」をご紹介していますが、各都道府県ごとに司法書士会があり、そこのHPで司法書士を探すこともできます。
6.沼津の司法書士貝原事務所が紹介する「相続登記の進め方」
(1)「相続登記の進め方」に関連する記事
土地・建物を相続した方々は、「相続登記」という「なんだか難しそうだけど、自分でやれなくもなさそうな手続き」に出会うことになります。
「自分でもできるかな」と思って、インターネットで検索すると、相続登記に関する記事がたくさん出てきます。
最近では、ご自身で相続登記を進めることをサポートするウェブ上のサービスも登場しています。
一方で、さきほどご紹介したように「どの土地・建物について相続登記をすればよいのか」というのは、ちょっとした知識や経験が必要となります。
そうした相続登記のポイントをお伝えするとともに、専門家に相続手続きを依頼したいと思ったときの相談先(司法書士)をアピールもしたいと思い、「相続登記の進め方」に関連する記事を作成しました。
この記事のほかにも、シリーズになっていますので、興味があれば、ぜひご覧ください。
(2)相続登記の進め方(沼津の司法書士が解説!)