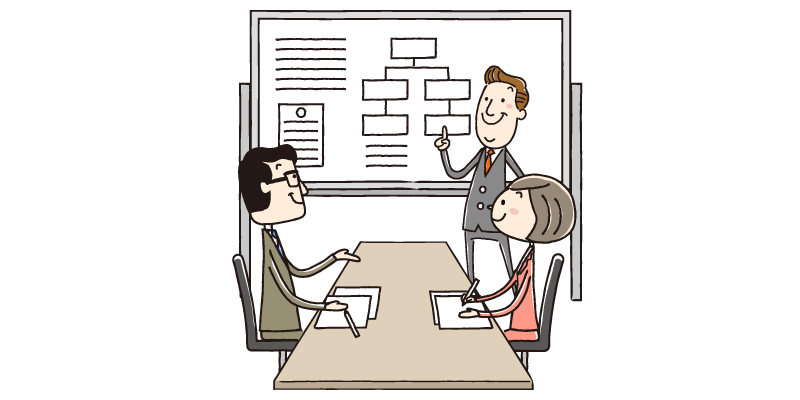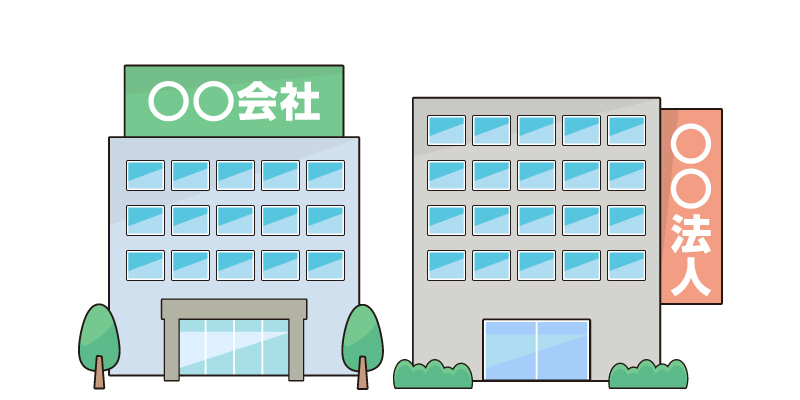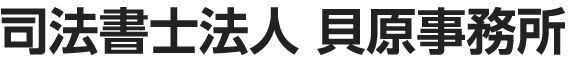目次を表示
会社設立の際に、依頼者様から、よく質問を受ける事項をまとめてみました。
1.会社の事業目的はどのように決定すればよいのか
会社の事業目的について、なにをどのように定めるかということは経営者自らが定める事項であり、法律上の決まりがあるわけではありません。
原則的には、会社は事業目的に記載された事業のみを行うことができるのですが、事業目的は非常に広く解釈されることとなっており、実際のところは、法的には、そこまで細かく事業目的に記載しなければならないというわけではありません。
(1)まずは、3つのポイントを押さえればOK。
事業目的については「登記をして一般の人にわかりやすく会社のことを教える」ということから、登記実務上、3つのポイントが要求されます。それは、①「明確性」、②「営利性」、③「適法性」です。
このうち、特に留意すべきなのは「明確性」です。
「明確性」とは「語句の意味が明瞭で一般人に理解できること」をいいます。
たとえば外国語や専門用語など、一般の人では内容を理解できない単語を用いようとするときには要注意です。
明確性を検討する際には、新語辞書など参照せよと言われていますが、最近は、新語の反映が追い付かないケースも多いように思います。
とりわけ技術発展の著しいデジタル技術関連分野においては、頭を悩ますことが多いです。
「営利性」が要求される趣旨は、会社が事業を通して利益をあげることを目的とした法人であることにあります。
たとえば、「政治献金」、「社会福祉への出資」などが営利性を否定され登記不可とされています。
「適法性」とは、法律上で目的として掲げることに制限や要件がもうけられていたりする事項を含まないことをいいます。
銀行でないのに「銀行営業」を目的に入れたり、弁護士や司法書士でないのに「登記申請の代理」を目的に入れたりすることは出来ません。
(2)事業を行うにあたり許認可申請が必要な場合
事業を行うにあたり許認可申請が必要な場合には、一定の事項が目的に記載されていることが求められます。建設業、旅行業、労働者派遣事業、古物商、介護保険事業などです。
したがって、こうした事業を行う際には、許認可申請に則した事業目的を記載することが必要となります。
(3)事業目的をたくさん盛り込みすぎると良くないのか?
会社設立後に、事業目的を変更する場合には、登録免許税が3万円必要となります(変更手続きを司法書士に依頼すると、さらに、司法書士への報酬も必要になってきます。)。
それを見越して、会社設立時になるべく沢山の事業目的を盛り込もうとする方がいらっしゃいます。事業目的には、「実際に行っている事業」だけではなく「将来行う可能性のある事業」も記載することができるからです。
しかしながら、事業目的が登記された謄本は、取引先や金融機関が見るものです。そうしたときに、本業と関係のない雑多な事項が盛り込まれている謄本は、非常に印象が悪いでしょう。
さらには印象が悪いというだけにとどまらず、融資を受ける際などに「余計な事業目的を削除してください」という指示を金融機関から受けたという話もあります(ということで当事務所に依頼をいただくというケースも。とりわけ「貸金業」など。)。
設立時には「現に行っている事業」と「将来高い確率で行う事業」に限定したほうがベターではないかと考えています。
(4)どのように事業目的を決定するのか
様々なソースを使って調べるということに尽きるのですが、次のような方法は有益です。
- 類似業種の会社の登記情報を取得してみる
- 類似業種の上場会社の定款を確認してみる(開示されています)
- 専門誌等で頻繁に使用されている単語かどうかを確認する
2.資本金はどのように決定すればよいのか
(1)資本金の金額は自由!
昔は、会社を設立するには株式会社では1,000万円(有限会社ならば300万円)の資本金が必要でしたが、会社法の施行により株式会社の資本金についての制限は無くなりました。
したがって、法律上の要件としては1円でもOKですので、まずは、対外的な信用を考慮して決めていくことになるかと思います。
(2)許認可や税務上のルールを確認
許認可を取得して事業を営む場合には、当該許認可にて資本金要件がある場合には、当然その要件をクリアする必要があります。
たとえば、建設業や労働者派遣事業など一定の形で資本金額が関与してくるものが該当します。
また、税務上は、消費税・法人住民税(いちおう登録免許税も)に関係してきます。
この点については、税理士さんにお任せして確認していく事項となります。
3.役員(取締役、監査役)はどのように決定すればよいのか
(1)最低1名いれば株式会社は設立可能
非公開会社(すべての株式に譲渡制限がかかっている会社)では、取締役は最低1名いればOKです。
そして監査役は必須ではありません。
そのため、株主兼取締役1名という会社は数多く設立されています。
旧法時代には、会社形態による信用度を考慮して株式会社を選択し家族や友人の方を名前だけの役員にすることがあったといわれますが、会社法においてはこのようなことをする必要はなくなりました。
(2)パートナーや親族を役員にすることも
そうなると純粋に経営的な側面から、会社を運営していく中で必要不可欠なパートナーを取締役・監査役として選任していくということになります。
一方で、税務上の観点から(観点のみで?)、親族を役員にする方もいらっしゃいますが、当然ながら取締役としての法的責任を負うことになるので、この点は注意が必要です。
4.取締役の任期はどのように決定すればよいのか
取締役の任期は原則2年ですが、非公開会社では、最大10年まで延長することができます。
役員の任期が満了するごとに(たとえ同じ人が役員であっても)役員変更登記が必要となりますので、任期が長ければ登記をする回数は少なくなり、その分の手間や費用が軽減できます。
一方で、取締役を任期中に辞めさせるには、自ら辞任する場合を除き、株主総会で解任するしかありません。
登記簿上「解任」という文言が載りますし、解任される取締役との間でトラブルとなる可能性があります。
従って、任期を検討する際には、上記のメリット・デメリットをふまえて決めていくこととなります。
【参照記事:会社設立時に検討すべき「取締役の任期」について】