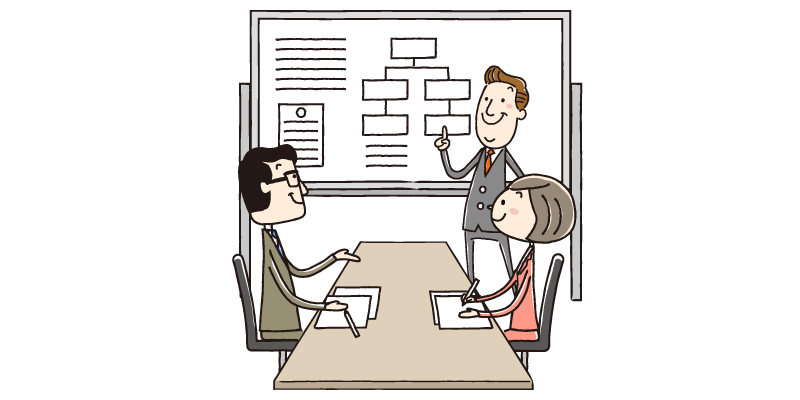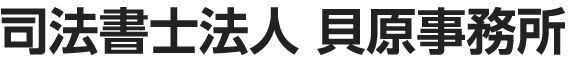目次を表示
1.成年後見制度とは
(1)成年後見制度は「判断能力が不十分な方をサポートする仕組み」
成年後見制度は、判断能力が不十分な方に対して、法的なサポートを提供する仕組みです。
一人暮らしをしている母の物忘れがひどくなってきた。
大切な預金通帳を何度も紛失するし、家の中には、なぜか銀行からおろしてきた現金が散乱している。
わたしの叔母は重い認知症となり、現在は施設に入所している。
施設利用料を捻出するために、叔母名義の不動産を売却したい。
とはいえ、叔母自身では、不動産の売却手続きを進めることはできない。
以上のようなケースについて、
モデルケース1では「日常的な金銭管理を代わりに行い、サポートしてくれる人」が、
モデルケース2では「不動産の売却手続きを代わりに行い、サポートしてくれる人」が必要となります。
こうした「サポートしてくれる人」を選任する仕組みが「成年後見制度」なのです。
(2)法定後見と任意後見
成年後見制度には、大きく分けて2つの種類があります。
- 法定後見制度:判断能力が衰えてから利用する制度(家庭裁判所がサポーターを選任)
- 任意後見制度:将来の破断能力低下に備えて利用する制度(あらかじめ自らサポーターを選任)
この記事では、法定後見制度について詳しく確認していきます。
そのため「成年後見制度」という場合、注記がない限りは、法定後見制度を前提としていますので、ご留意ください。
また、任意後見制度について知りたい方は、下記リンク先の記事をご覧ください。
【参照記事:任意後見契約について】
(3)成年後見制度と「沼津の司法書士貝原事務所」の関係
「司法書士」の業務は、成年後見制度と次のような関わり合いをもっています。
- 成年後見等開始申立書の作成サポート
(法定後見の利用のために家庭裁判所に申立てをおこなう場面) - 成年後見人等への就任
(成年後見人等として実際にサポーターとして活動する場面)
とりわけ2点目の「成年後見人等への就任」に関しては、職種としては「司法書士」が最も多く家庭裁判所から選任を受けています。
当事務所(沼津の司法書士貝原事務所)においては、申立支援や後見人等への就任はもちろんのこと、親族後見人の活動支援もおこなっています。
【参照記事:司法書士による成年後見制度の利用サポートについて】
2.成年後見制度の利用について考える
(1)どんな人が成年後見制度を利用しているのか?
成年後見制度を利用する方は様々ですが、大きく分ければ、つぎのようになると考えます。
- 具体的な法的課題をクリアするために成年後見制度を利用するケース
- 日常生活全般に関するサポーターを必要としているケース
くわしくは、各号で確認していきます。
(2)具体的な法的課題をクリアするための後見利用
認知症や精神障害が原因となって、お一人では法的な意思表示ができない方は、つぎのようなケースで困ることになります。
- 【ご本人が保有する不動産の売却】
ご本人名義の不動産を売却したいが、法的な意思表示ができないため、売買契約を結ぶことができない。
⇒<参照記事:不動産売却にあたり、成年後見人の選任を求められた場合> - 【ご本人が相続人となる遺産分割協議の実施】
ご本人が相続人の1人となっているが、相続の分け方に関する話合い(遺産分割協議)において法的な意思表示ができないため、相続人全員が遺産の分け方を決めることができない。
⇒<参照記事:遺産分割協議を進めるために成年後見人の選任を求められた場合> - 【ご本人名義の定期預金の解約】
ご本人名義の定期預金を解約したいが、法的な意思表示ができないため、銀行窓口で手続きを拒否されてしまった。
⇒<参照記事:定期預金の解約に際して、成年後見制度の利用を求められた場合>
ご本人の財産が活用できないとか、相続財産が凍結されたままといった状況では、ご本人が困ることは当然として、周辺の支援者や相続人も困ったことになってしまいます。
そこで成年後見制度を利用し、法的な意思表示ができない方をサポートする人間を家庭裁判所に選任してもらうことで、止まっていた各種手続きを進めていこうということになるのです。
(3)日常生活全般に関するサポーターを選ぶための後見利用
沼津市内で一人暮らしをしているAさん。
数年前に夫を亡くし、近くに身寄りはいません。
認知症の症状が重くなってきており、施設入所を検討しています。
「身寄りがいない方」「身寄り入る者の、なんらかの事情で生活サポートを受けることができない方」が成年後見制度を利用するケースです。
とりわけ、重い認知症を患った高齢の方で、近くに生活をサポートしてくれる親族がいないケースだと、法的な課題や生活環境を整理・整備するサポーターの存在が必要不可欠です。
そうしたサポーターの一人として成年後見人が求められるケースがあります。
3.成年後見制度の利用と費用(お金)
(1)成年後見制度をスタートさせるときのお金・費用
成年後見制度の利用は、家庭裁判所に対する「後見等開始の申立て」によります。
この「後見等開始の申立て」をする際には、家庭裁判所に対して所定の費用を収入印紙や切手で納める必要があります。
家庭裁判所に納める費用は、類型によって異なりますが、概ね1万円前後です。
これに加えて、申立て手続き全般を弁護士に代理してもらったり、あるいは申立書類の作成を司法書士にサポートしてもらったりすると、それぞれ弁護士や司法書士に対する報酬が必要となってきます。
このほかにも、つぎのような費用を考慮する必要があります。
- 申立書に添付する、医師の診断書の作成費用。
(5000円くらいのところが多いように思いますが、診療所・病院によって異なります。) - 家庭裁判所における審査の中で「医師による鑑定」が必要となった場合の鑑定費用。
(必ず鑑定が必要になるわけではありません。鑑定費用は5~10万円と案内している家庭裁判所が多いです。)
(2)成年後見制度を利用しているときのお金・費用
成年後見制度を利用していく中でかかる費用の代表格は「成年後見人への報酬」です。
この点については、つぎの記事をご参照ください。
(3)成年後見制度の利用に伴う費用はご本人が負担
成年後見人の報酬や、成年後見人がご本人のために行った事務の費用は、ご本人が負担することになります。
当事務所にて、後見開始の申立てをサポートする際に、申立人となる親族の方から「選ばれた後見人の報酬を申立人となった自分(ご親族)が負担しなければならないのか?」と聞かれることがよくあります。
この点については、明確に「NO(親族が後見人の報酬を負担する必要はない)」ですので、ご安心ください。
4.成年後見制度の利用の仕方
(1)家庭裁判所への申立て
成年後見制度の利用をする場合には、管轄する家庭裁判所に「後見等開始の申立て」を行います。
管轄裁判所は、裁判所のHPで確認することができます。
たとえば静岡家庭裁判所・沼津支部の管轄は、次のとおりです。
沼津市・御殿場市・裾野市・駿東郡(清水町 長泉町 小山町)・三島市・伊豆市・伊豆の国市・田方郡(函南町)
当事務所(沼津の司法書士貝原事務所)の近隣では沼津支部のほか、富士支部・下田支部・熱海出張所があります。
申立てについて詳しく知りたい方は、つぎの記事をご参照ください。
【参照記事:成年後見人選任の申立てについて】
(2)誰が家庭裁判所に後見開始の申立てをするのか
家庭裁判所に対する後見開始の申立てについては、申立てをすることができる人(申立権者)が法律で限定されています。
主な申立権者は、次のとおりです。
- ご本人
- 配偶者
- 4親等以内の親族
- 市区町村長 など
なお、先ほども述べましたが、申立権者になったからといって、専門職後見人への報酬を負担しなければならないということはありませんので、ご安心ください。
5.成年後見制度を利用するときに必要な書類
後見開始の申立てにあたっては、申立書のほか、いくつかの書類を添付書類として家庭裁判所に提出する必要があります。
主なものをご紹介します。
申立書類や添付書類について詳しく知りたい方は、つぎの記事をご参照ください。
【参照記事:成年後見人選任の申立てについて】
(1)医師の診断書
医師の診断書は、ご本人の類型判断のために利用されます。
類型について、詳しい内容を確認したい方は、つぎのページをご参照ください。
【参照記事:法定後見(後見・保佐・補助)と3類型について】
大まかに説明すれば、法定後見は、ご本人がサポートを必要とする度合いに応じて「後見」「保佐」「補助」という3類型に分類されています。
分類ごとにサポーターの権限の範囲が変わってくるのです。
家庭裁判所は、「医師の診断書」を判断資料の一つとして、いずれの類型にするのか決定します。
(2)収支予定表・財産目録
収支予定表や財産目録は、ご本人が置かれている状況を確認するための資料です。
単に「収支予定はこうなっています」「財産はこれくらいあります」というだけではなく、裏付けとなる資料(年金証書・施設利用料請求書・預貯金通帳などのコピー)も提出します。
(3)親族の意見書
親族の意見書とは、推定相続人(申立て時点でご本人が亡くなったと仮定したときに、ご本人の相続人となる人のことをいいます。)から、後見制度利用や後見人候補者への賛否を確認するために提出するものです。
とりわけ、ご親族が後見人になることを希望するケースにおいては、意見書の有無や内容が重要になってきます。
制度利用について反対する親族がいたり、特定の親族が後見人になることについて反対する親族がいる場合には、親族後見は難しいと言わざるを得ません。
6.成年後見人には誰がなればよいのか
(1)成年後見人となるのに職業資格は不要!
法律上、成年後見人となるのに、弁護士とか司法書士といった職業資格は不要です。
そのため、家庭裁判所から選任されれば、親族はもちろんのこと、一般の方でも成年後見人となることができます。
では、誰でもなれるのかというと、そうではありません。
民法という法律において、つぎの欠格事由が定められています。
- 未成年者
- 破産者 などなど
(2)親族が後見人になりたいなら「候補者」となる必要がある
成年後見人は、親族も家庭裁判所から選任を受ければなることができます。
ここで注意したいのは、親族が後見人となることを希望するのならば、家庭裁判所に後見利用の申立書に「候補者」として記載しておく必要があるということです。
候補者として記載しなくても家庭裁判所が親族を後見人に選任する可能性も無くはないと思いますが、通常は、「候補者として親族が後見人への就任を希望していること」「親族の意見書において、その者の就任に他の親族が反対しないこと」を家庭裁判所に伝える必要があるでしょう。
また、以前は、「ご本人に一定の財産があると、それだけで親族が後見人となることができない。」と言われることもありましたが、現在では運用が変わっています。
家庭裁判所が公表している統計情報(※)をみても、令和3年に新たに成年後見人等が選任された事案において、親族が後見人候補者となった事案が全体の23.9%。
そして親族が選任された事案が全体の19.8%でした。
候補者として記載されれば、親族等の反対などが無い限りは、親族が選任されているものを推察されます。
親族後見について、より詳しく確認したい方は、こちらのページをご参照ください。
【参照記事:親族後見と選任パターンについて】
※:「成年後見関係事件の概況―令和3年1月~12月―」最高裁判所事務総局家庭局
(3)成年後見人としての「専門職後見人」の特徴
家庭裁判所が公表している統計情報(※)をみると、令和3年に新たに選任された成年後見人等のうち約66%が、いわゆる「専門職後見人」となっています。
専門職後見人とは、割合の多い順番に、つぎの3職種の者が後見人となることをいいます。
- 司法書士
- 弁護士
- 社会福祉士
専門職後見人の特徴としては、司法書士・弁護士においては「相続や不動産売却など法的課題の整理が得意」、社会福祉士においては「福祉・障害などの各分野における課題解決が得意」といった点をあげることができます。
各専門職が、自身の特長を活かして後見活動ができるのが大きなメリットですが、たとえば親族後見人と比較すると、(とくに司法書士や弁護士などの法律職において)身上保護面でのサポートが不足しがちとの指摘を受けることがあります。
※:「成年後見関係事件の概況―令和3年1月~12月―」最高裁判所事務総局家庭局
7.成年後見人にはできないこと(権限外の行為)
(1)直接の介護・看護などの事実行為
成年後見人は、法的な権限を駆使して、ご本人の生活をサポートすることが仕事です。
そのため、直接にご本人を介護したり、看護したりすることは、後見人の職務ではありません。
ご本人に介護や看護が必要な状態であれば、後見人はご本人が必要な介護・看護を受けられるように介護施設や医療機関と契約することが、後見人の職務となります。
(2)身分行為
身分行為というのは、たとえば「婚姻」や「養子縁組」など、身分関係に変動を生じさせる行為を指します。
身分行為は、本人のみが決定権を持つことがらであり、誰かが代わって決定するべきものではありませんん。
そのため、成年後見人の権限の範囲外ということになります。
(3)医療同意
たとえばワクチン接種をするとき記入する問診票には、その下のほうに「接種を希望するか否か」をチェックする欄があります。
新型コロナワクチンの問診票にも「医師の診察・説明を受け、接種の効果や副反応などについて理解した上で、接種を希望しますか」という同意確認の文章があります。
ワクチン接種だけでなく、たとえば大きな手術をするときなどにも、このような「医療行為に関する同意」を求められているはずです。
こうした「医療行為に関する同意」というのも、自分自身のみが決めるべき事柄であり、誰かが代わって決めるべき事柄ではありません(たとえば外科手術などは、ある意味で自分の体を傷つける行為ですが、こうした行為を他人が代わって許可できるとしたら・・・)。
8.成年後見人になったら
(1)成年後見人に就任した直後にすること
就任した直後にすべき主な業務はつぎのとおりです。
- ご本人の生活状況や財産状況を調査し把握すること。
- 役所や金融機関などに後見人就任の届出をすること。
- 上記2つの作業を通して財産目録・収支予定表を作成すること。
- 作成した財産目録・収支予定表などを家庭裁判所に報告すること(いわゆる初回報告)。
家庭裁判所に対する「初回報告」は、家庭裁判所から指定される期日までに提出する必要があります。
2ヶ月程度の期間を定められることが一般的ですが、上記1・2の作業をしていると、あっという間に期限がきてしまいます。
早め早めに対応を進めていきましょう。
また、初回報告をするまでの間は、後見人は「(ご本人にとって)急迫の必要がある行為」(民法854条)のみをする権限しかないことにも注意が必要です。
(2)成年後見人としての活動
初回報告以降は、後見人としての通常業務を行っていきます。
後見人としての通常業務は多岐にわたりますが、たとえば、つぎのようなことを行っていきます。
- 預貯金の管理
- 年金や給付金・手当金などの定期的な収入の管理
- 施設利用料・入院費・水道光熱費・税金などの定期的な支出の管理
- ご本人が利用する介護サービス・医療サービスのチェック
(必要なサービスを受けることができているか。サービスの提供は適切になされているか。など)
以上のような定期的な業務のほかにも、つぎのような事項に対応することもあります。
- ご本人の保有する不動産の処分
- ご本人が相続人となる相続手続きの実施
9.成年後見制度の終了
(1)成年後見制度が終了するとき
成年後見制度は、一度利用を開始すると、原則としてご本人が亡くなるまで継続することになります。
それでは、ご本人が亡くなったとき(成年後見制度が終了するとき)には、成年後見人は何をするのでしょうか?
ここでは、終了時の成年後見人の職務を簡単に確認していきます。
(2)ご本人が亡くなった際の後見人の職務
ご本人が亡くなったことにより、成年後見人としての権限はなくなります。
それまで、成年後見人として管理していたご本人の財産は、ご本人の相続人に管理権限が移ることになるのです。
そこで、成年後見人は次のような順序で、自らの職務について整理したうえで、相続人に管理財産を引き渡すことになります。
- 「管理の計算」を行います。
これは、成年後見人として就任したときから職務が終了するまでの収入支出を計算し、就任中の財産の変動と終了時点の財産を、相続人に対して報告するものです。 - 「相続人の調査」をおこないます。
誰がご本人の相続人であるか調査しなければ、「管理の計算」の報告を行うこともできません。
通常は、管理の計算と並行して相続人調査を進めます。
「管理の計算」と「相続人の調査」をしたうえで、相続人への財産の引渡しをおこないます。
というのが、教科書的な説明になるのですが、とりわけ身寄りのない方の後見人をしていると、ご本人様の火葬などの「死後事務」への対応も求められることになります。
この点については、つぎの記事もご参照ください。
【参照記事:成年後見人と葬儀・埋葬について】
(3)相続人への財産の引渡し
成年後見人が管理していた「ご本人の財産」は、ご本人の死亡とともに「相続財産」となっています。
相続財産の管理は、相続人が行うべきものであり、そのため成年後見人(であった人)は相続人に対して管理財産の引渡しを行う必要があるのです。
ただし、遺言書の有無によっては、相続財産の引渡し先が相続人以外の第三者となるケースもあります。
また、相続人が複数いる場合にも、「相続人のうちの誰に引渡しをすればよいのか」も判断しなければなりません。
(4)家庭裁判所への終了の報告
相続人等への財産引渡が完了すれば、成年後見人としての職務はすべて終了ということになります。
成年後見人(であった者)は、職務が終了したことを、管轄する家庭裁判所に報告します。
なお、実務上は、とりわけ専門職が成年後見人を務めているケースでは、つぎのような流れをたどることもあります。
- 管理の計算の実施
- 計算結果を「家庭裁判所」に報告。
同時に、最後の報酬付与の審判を申立てる。 - 最後の報酬付与の審判を受けたうえで、成年後見人から相続人等に管理財産の引渡しを行う。
- 成年後見人から相続人等への引渡しが完了したことを家庭裁判所に報告する。
10.成年後見制度の利用を検討する際には
ここまで成年後見制度の基礎的な部分を確認してきました。
基礎的な部分といっても、かなりのボリュームになってしまいました。
一方で、説明が物足りない部分があった方もいるでしょう。
具体的に、
「親族について成年後見制度の利用を検討したい」とか「自分自身が親族の成年後見人となりたい」といった思いを持った場合には、是非とも司法書士をはじめとする法律専門職に相談しながら、手続きを進めていってほしいと思います。