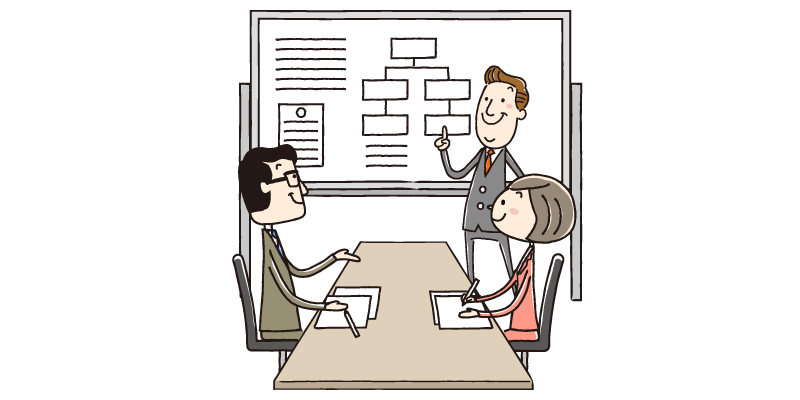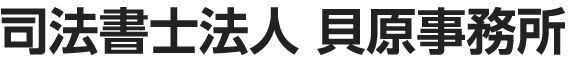目次を表示
1.成年後見制度を利用して不動産を売却?!
(1)介護費用捻出のため母親の不動産を売却したい!
三島市にお住いのAさん。
Aさんは、母親Bさんの介護費用を捻出するため、Bさんの所有する不動産を売却したいと考えています。
ところがBさんは重度の認知症で、自ら売買契約の当事者になることはできません。
どうしようかと近所の不動産屋さんに相談しに行ったところ、「成年後見制度を利用してください」と言われてしまいました。
Aさんは「成年後見制度??」という状態です。
とはいえ、お母さんのためにも不動産を売却する必要があり、後見制度利用のために司法書士に相談に行くことになりました。
Aさんのように、不動産を売却する必要性に迫られている状況において「成年後見制度を利用してください」といわれてしまうと、何はともあれ「成年後見制度を利用するんだ。不動産を売却するんだ。」という考えに陥りがちです。
慌ててしまう気持ちもわかりますが、まずは一呼吸おいてみましょう。
こうした場合に、考えるべき点は2つです。
- 成年後見制度の基本を理解する。
- 「成年後見制度を利用して今すぐに不動産を売却する必要性」と「成年後見制度を利用するメリット・デメリット」を比較する。
なお成年後見制度には、いくつかの種類・類型がありますが、この記事では「後見類型」であることを前提に記載しています。
種類・類型について詳しく知りたい方は、つぎの記事をご覧ください。
【参照記事:法定後見(後見・保佐・補助)と3類型について】
(2)成年後見制度の利用にあたっては不動産売却以外のことも検討すべき
成年後見制度は、認知症のご本人(モデルケースでいう母親B)に代わって不動産を売却するためだけの制度ではありません。
まずは2つのポイントを確認しましょう。
- 成年後見人は、不動産だけでなく、預貯金なども含めた、ご本人の財産全体を管理する。
- 不動産売却の目的で後見制度を利用した場合であっても、不動産売却後も成年後見人の活動は続く。
とくに2点目は重要です。
いったん後見制度の利用を開始すると、基本的にはご本人が亡くなるまで利用を継続する必要があります。
そのため、不動産売却のことだけを考えて後見制度を利用するのではなく、後見制度を利用した場合に、ご本人(モデルケースでいう母親B)の生活にどのような影響があるのかを考えていかなければならないのです。
2.成年後見制度と不動産売却について
(1)成年後見制度を利用して「ご本人の代理人を選任してもらう」
認知症等の影響により、法的判断能力が不十分な方は、自ら不動産売買契約を締結することはできません。(そして、子供だからといって、親の財産を勝手に売却できるわけでもありません。
そこで、法的判断能力が不十分な方に対しては、成年後見制度を利用し、成年後見人等を選任します。
選任された後見人等が、不動産売却の必要性などを検討したうえで、ご本人に代わり代理人として売却の手続きを進めていくのです。
(2)成年後見人は何をする人なのか?どんな権限があるのか?
成年後見制度は、判断能力が不十分な方に対して、法的なサポートを提供する仕組みです。
すでに法的な判断能力が不十分な状態となっている方に対して、家庭裁判所がサポーターを選任する仕組みを「法定後見」といいます。
法定後見は、サポーターの権限の範囲によって、さらに3つの種類に分かれます。
このうち、サポーターの権限の範囲が最も広いのが「後見」類型です。
後見人は、ご本人の財産全般に対する代理権をもつことになります。
3.成年後見制度を利用するには(家庭裁判所への申立て)
(1)家庭裁判所への申立て
成年後見人を選任するには、まず家庭裁判所に対して選任の申立てをします。
申立てをする資格がある者は法律上限定されており、代表的な人には「配偶者」「4親等以内の親族」がいます。
申立てを受けて、家庭裁判所は成年後見人を選任します。
この際、医師からの診断書を添付し、基本的には診断書に基づいて3類型(後見・保佐・補助)のいずれに該当するか判断します。
(2)後見人等候補者を記載することができる
また、申立に際しては「後見人等候補者」を記載することができるので、候補者欄に親族を記載することもできます。
後見人を誰にするかは、最終的には家庭裁判所が決定することですが、後見人になるために法的な資格は要求されないので、事案によっては候補者欄に選任された親族が後見人となることも可能です。
4.不動産の種類により「家庭裁判所の許可」の要否が決まる
申立てによって、成年後見人が選任されたからと言って、ただちにご本人の不動産売却ができるわけではありません。
選任された成年後見人は、まず自ら調査して不動産売却の必要性・相当性を検討します。
ここで注意したいのは、売却する不動産が「居住用不動産」である場合には、売却にあたって家庭裁判所の許可が必要となるということです。
居住用不動産であるにもかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで売却してしまった場合には、売買契約自体が無効となります。
「非居住用不動産」については、家庭裁判所の許可は不要であるものの、重要財産の処分に該当するため、事前に家庭裁判所と協議して「根回し」をしたうえで売却手続きを進めるのが実務的な対応となっています。
(後見監督人がついている事案においては、後見監督人の同意が必要になります。)
5.不動産売却が完了しても後見業務は継続
必要なステップを踏んで、後見人によって不動産売却が完了しても、そこで後見制度の利用が終了するわけではありません。
後見制度は、ご本人にとって必要な限りは継続するため、認知症等が回復するか、あるいはご本人が死亡するまで継続することになります。
親族が後見人となっているケースでは、後見人としての業務を継続することが必要となります。
専門職後見人が就任しているケースでは、専門職後見人の報酬が発生してきます。
6.最初のモデルケースの解決例
Aさんは、あらためて司法書士事務所に相談に行き、母親Bさんに対する後見人選任の申立てを行うことにしました。
申立てにあたっては、司法書士から後見人の職務内容や責任について十分な説明を受けたうえで、Aさん自身を候補者として記載することとしました。
結果として、Aさんが後見人に選任され、さっそく不動産売却の手続きを始めることになったのです。
売却を予定していた不動産は、Bさんの居住用不動産に該当したため、司法書士のサポートも受けながら「居住用不動産の売却許可」を家庭裁判所から取得しました。
その後、Aさんが母親Bさんの成年後見人として売買契約を締結し、無事、不動産を売却することができました。
売却によって得たお金は、Aさんが成年後見人として管理するBさんの口座に入金し、また不動産売却後も、Aさんが成年後見人として、Bさんの財産管理・身上保護を行っていくこととなります。
この事例に関連する記事